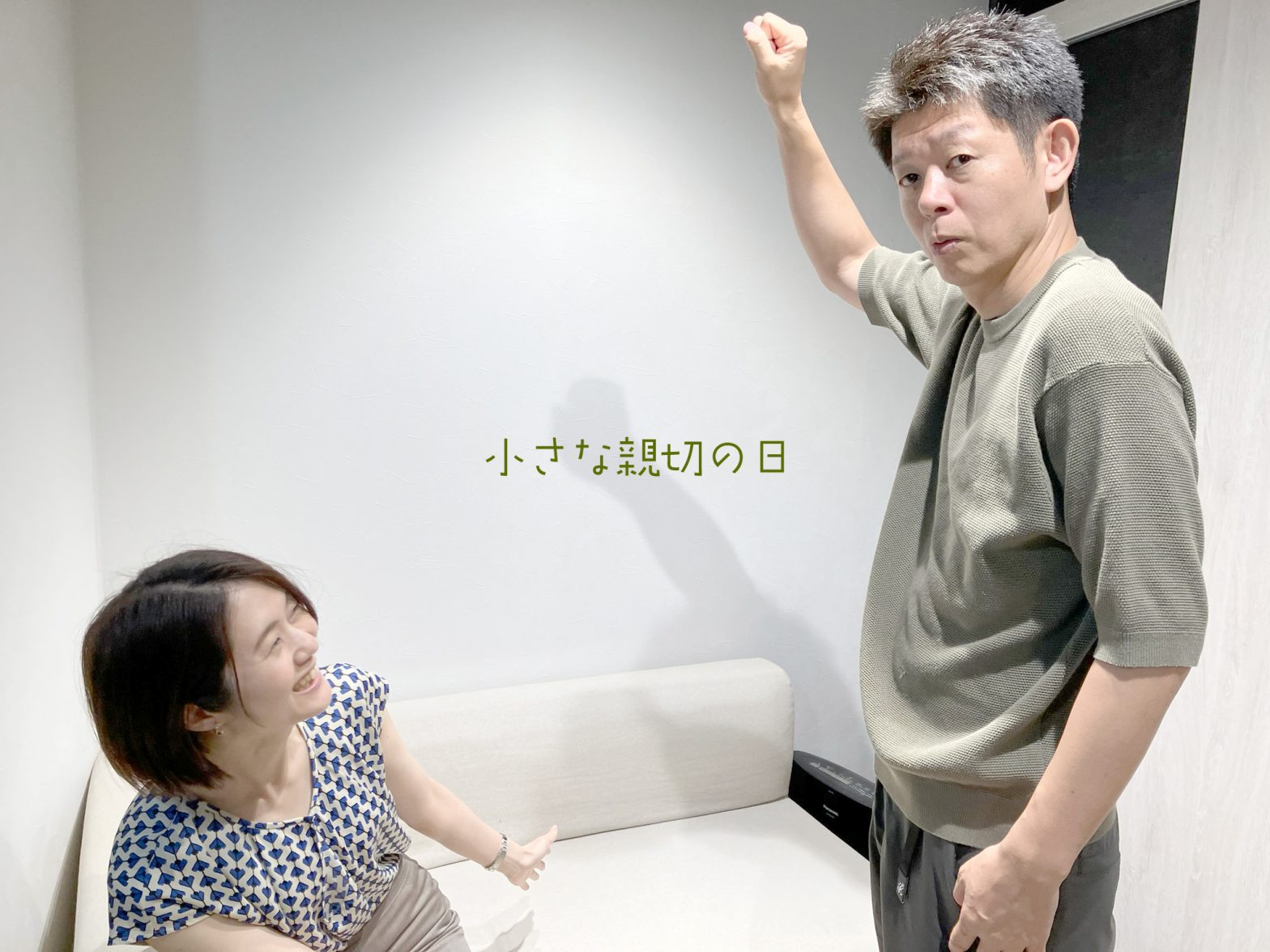放送日の8月4日は「栄養の日」でした。弁護士は忙しいイメージがありますが、古藤先生に食事について伺ったところ「できるだけ取るように心掛けています」とのこと。やはり忙しさはイメージ通りのようです。栄養を取って、健康第一で頑張っていただきたいですね!ちなみに、お昼を取る時には、裁判所の食堂や弁護士会のレストランのほか、東京であれば裁判所の周りの「各省庁の食堂」に行くことが多いそうです。中でも農林水産省の食堂はとても美味しいのだとか。さすが農林水産省ですね…。一般の人でも行けるとのことですから、これはぜひ行ってみたいですね!
さて、第146回の放送で「侮辱罪」について古藤先生に解説して頂きましたが、いよいよ今年7月7日、インターネット上の誹謗中傷対策を強化するため、侮辱罪の法定刑の上限を引き上げる改正刑法が施行されました。ネット上の中傷は匿名で行われることが多く、加害者の特定に時間がかかるため、厳罰化による抑制効果に加え、立件の可能性が高まることが期待されています。
第184回の放送では、侮辱罪に関する変更点と、自身が被害者・加害者になってしまった場合の対処法について、古藤先生に詳しく解説して頂きました。
侮辱罪とは?侮辱罪の成立条件
「侮辱罪」とは、“事実を摘示しなくても公然と人を侮辱した”時に成立する犯罪を指すそうです。「公然」とは、“不特定又は多数人が知り得る状態”という意味です。インターネットやSNS上の書き込みなども “不特定の誰かに対して知らせること”になりますから、実際の閲覧数に関わらず「公然」に該当するとのことです。またここでいう「多数人」は文字通り“たくさんの人”という意味ですが、特定少数人にのみ知られる状態であったとしても、そこからより多くの人に拡散される可能性を考慮して、侮辱罪の成立を認めた判例(最高裁判例 昭和34年5月7日)があるそうです。
一方で、一対一の場や、ダイレクトメッセージのように直接相手に届ける形のものは侮辱罪の対象になりません。
侮辱罪と名誉毀損の違い
侮辱罪と名誉毀損罪の違いは、社会的評価を貶めるための手段として「事実を摘示するかどうか」ということだそうです。「事実の摘示」とは、“具体的な事柄もしくは言動を事実として周囲に伝える行為”を指します。つまり、侮辱罪は、具体的な事実が無くとも、誹謗中傷や暴言だけで成立するそうです。
また、「侮辱」とは“他人の人格を蔑視する価値判断を表示する”ことで、例えば、「アホ」「バカ」「クズ」といった言葉、容姿や身体的特徴を指摘するような「チビ」「ハゲ」「デブ」といった言葉が侮辱に当たります。これは、言った当人の意思にかかわらず、言われた方が「侮辱された」と感じた場合には罪として訴えることが出来ます。侮辱罪は親告罪であるため、被害者による告訴手続きが必要になるそうです。
侮辱罪厳罰化の背景と変更点
今回、侮辱罪が厳罰化されることになった背景には、インターネットやSNSでの誹謗中傷被害の深刻化があるとのことです。ニュースなどでも頻繁に取り上げられていますよね。そんな中、現行の侮辱罪では法定刑が軽すぎるとして、厳罰化が議論されてきましたが、改正刑法の施行により、侮辱罪が厳罰化されることになりました。
今回の刑法改正では、次のような点が変わっているそうです。
1.罰則の追加
これまでの罰則は「30日未満の拘留、または1,000円以上1万円未満の科料」でしたが、改正後は、「1年以下の懲役・禁錮、または30万円以下の罰金」が追加されました。
これまで9,000円程度の科料で処理されていたケースには、より多額の罰金刑が科されることになり、非常に悪質だったり、罰金刑を受けた後にまた侮辱を繰り返して検挙された場合などには、懲役・禁錮刑が科されるようになるそうです。
2.公訴時効の延長
公訴時効が1年から3年に延長となりました。
これにより、長期間かかる投稿者の特定作業後の立件にも余裕ができそうとのことです。
3.教唆犯・幇助犯の処罰
侮辱した本人だけでなく、侮辱をするように唆した人や、侮辱するのを助けた人も処罰されるようになります。これまでは、侮辱罪の法定刑が拘留及び科料にとどまっていたため、刑法第64条により、特別の規定がない限り、教唆犯や幇助犯は処罰されませんでしたが、侮辱罪の法定刑に懲役・禁錮・罰金が追加されたため、特別の規定なくして、教唆犯や幇助犯を処罰することができるようになったそうです。
誹謗中傷された時の対処法
誹謗中傷の被害を受けた場合の対処法についても伺いました。
古藤先生によると、刑事事件として相手の処罰を求めたり、民事上の損害賠償を求めたりするためには、証拠が必要になるそうです。SNSなどでの投稿は容易に消されてしまうため、スクリーンショットを撮るなど、出来るだけ証拠を残すことが必要とのことでした。
ただ、投稿者を特定するには個人では難しい手続きが必要になるため、弁護士に相談することをお勧めしますとのことでした。弁護士であれば、「SNSや掲示板の運営者等に対して削除請求をする」、「発信者情報開示請求をして投稿者を特定し、損害賠償請求、削除請求、差止請求、謝罪を求める」などができるそうです。
誹謗中傷してしまった時の対処法
逆に、「誹謗中傷をしてしまったと思った時」にも、早い段階で弁護士に相談するのが良いとのことです。今後はSNSやオンライン上の侮辱罪の適用が増える可能性が高くなると思われるため、自分では“意見を述べただけ”のつもりでも、相手から侮辱罪として問われる可能性があるとのことです。
もし、誰かを侮辱する書き込みをしてしまったと思った時には、「できるだけ速やかに投稿を消し、相手方に謝罪をすること」「投稿を消す際には、後からどのような投稿をしたのかを確認できるよう、スクリーンショットなどを残しておくこと」が大切だそうです。弁護士に相談する際、具体的な投稿とその前後の文脈がわかならなければ、侮辱や名誉毀損に当たるかどうかの判断ができないため、前後の流れも含めたスクリーンショットがあるとスムーズとのことでした。
「侮辱された」時、逆に「侮辱してしまった」時には、なるべくお早めに弁護士にご相談ください。ひとりで悩むよりも、まずは気軽に専門家に聞いてしまいましょう!
困った時には、ぜひ、弁護士法人・響まで!