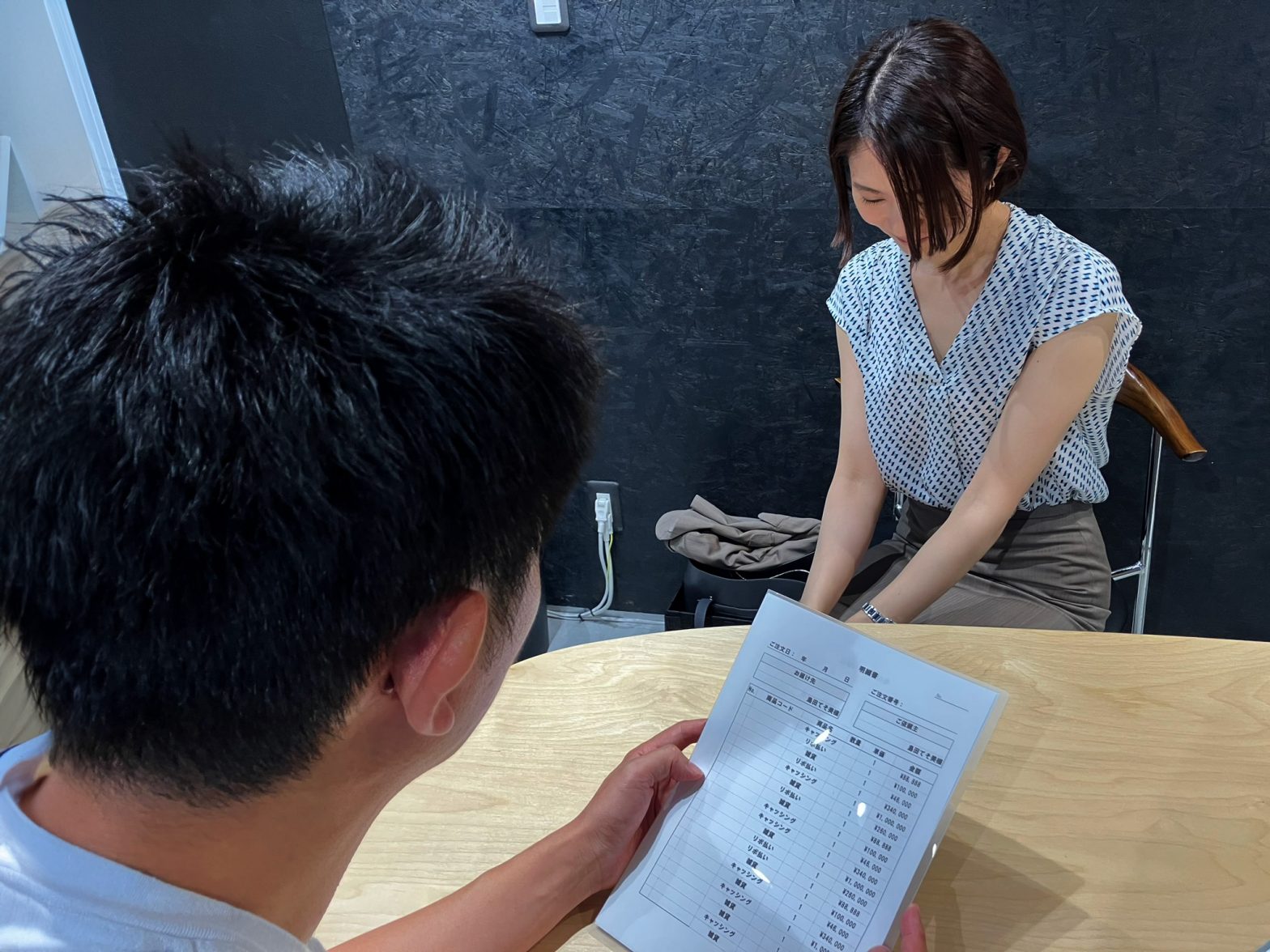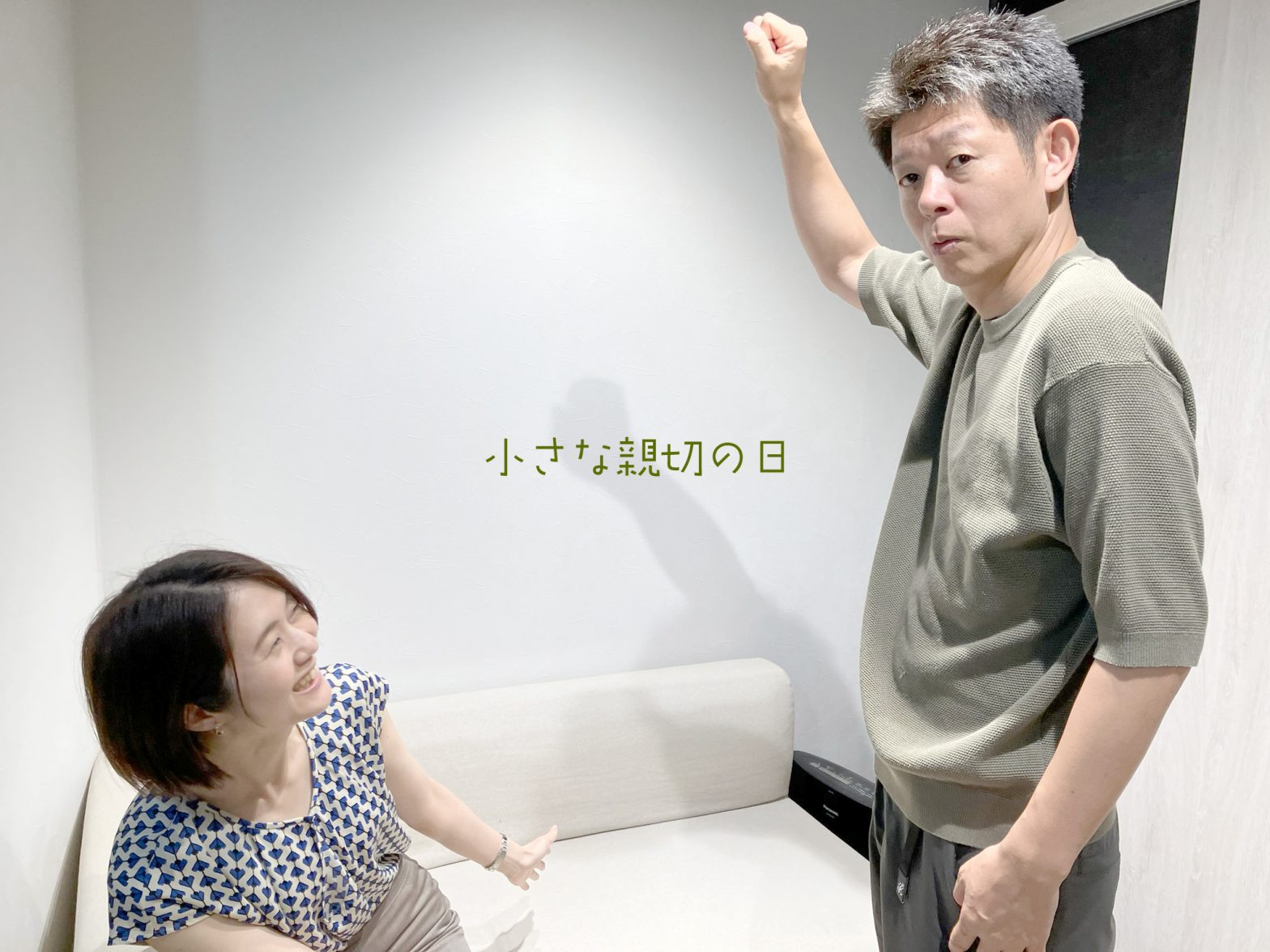第189回の放送も、弁護士法人・響の古藤由佳先生と一緒にお届けしました。
シルバーウィークがやってきますが、皆さまはどのようにお過ごしでしょうか。
古藤先生は決まったご予定は無いそうですが、ゆっくり温泉に入りたいとお休みの度に思っていらっしゃるそうです。そんな古藤先生にと、島田さんが紹介してくださったのは「秩父の三峯神社にあるお風呂」。神社のお風呂なんて、なんだかご利益がありそうですよね!
さて、オープニングは縁起の良いお話でしたが、今回のテーマは少しドキドキするお話です。
「事故物件」という言葉を聞くと、怪談やホラー映画などを連想する方も少なくないのではないでしょうか。番組でも、島田さんが怪談で語ってくださったことがありました。
今回は、そんな「事故物件」について法律的観点から古藤先生に解説して頂きました。
“事故物件”の告知義務とは?
古藤先生によると、「他殺や自殺、事故死などがあった、いわゆる“事故物件”の不動産を売却、又は賃貸する時には、売主・貸主はその事実を買主・借主に伝えなければいけない」という告知義務があるそうです。これは、特に居住用の不動産だと、心理的な抵抗の有無が契約の判断に大きく影響することが理由とのこと。
近年、高齢化により孤独死などが社会問題化する中、この事故物件の定義や告知義務の範囲に注目が集まっているそうです。
これまでの告知義務は「取引の相手方にとって契約締結の判断に重要な影響を及ぼす事実については告知しなければならない」という程度のルールしかなく、告知すべき事故の範囲や、発生後どのくらいの期間告知するかという具体的なルールは明確にされていなかったそうです。そのため、後になって事件の事実を知った買主が、売主に損害賠償を請求したり、貸主が孤独死を恐れて高齢者の入居を拒む自体が発生するなど、不動産の円滑な取引の妨げになっていました。
そこで、業界一律の基準を示そうと、令和3年10月、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が作られたそうです。
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
■告知義務の対象
ガイドラインでは、「居住用不動産の買主や借主が契約締結するかの判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事実は告知すべき」という原則は変わっていません。ただ、例外的に告知をしなくていい場面が具体的に示され、例えば「自然死」や、「日常生活の中での不慮の死」については、原則として告知義務なしとされたそうです。これには、病気や老衰で亡くなった場合も含まれます。
さらに、事故死の中でも「階段からの転落」や「入浴中の転倒」、「食事中の誤嚥」など、日常生活の中の不慮の事故についても同じく告知義務なしとされているそうです。ただし、このようなケースでも、発見が遅れたことにより遺体の腐乱が進み、臭気や害虫が発生するなどして特殊清掃が必要になった場合には、告知義務があるということでした。
■告知すべき期間
告知が必要な期間については、これまで明確なルールがありませんでした。
今回示されたガイドラインでは、賃貸物件で告知すべき事案が発生した場合、その発生から「おおむね3年間」は借主に対してこれを告知するべきと明記しているそうです。つまり、3年の内に何人借主が変わったとしても、貸主には告知義務があります。
ただし、これは賃貸の場合であり、売買契約に関しては、3年間などの期間の定めは設けられていないそうです。そのため、売り物件の場合は宅地建物取引業者が調査し、判明した事象について、買主に告げることになります。これは、売買は賃貸に比べてトラブルになった場合の損害額が大きいためだそうです。
■告知義務の範囲(場所)
ガイドラインでは、アパートのような集合住宅の場合、ベランダ、共用玄関、エレベーター、階段、廊下などの内、日常使用する場所は告知義務の対象に含まれているそうです。しかし、これまでの裁判例をふまえて、自分が契約する部屋以外で自殺があったことなどを賃借希望者に告知する義務はないと判断されているとのこと。
マンションでも、日常生活で通常利用しない共用部分や、戸建ての場合の隣接物件における事件・事故、および自然死で特殊清掃が必要な場合については、告知義務の対象外となっているそうです。日常生活から遠い場所については、義務の程度が低くなっているんですね。
ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響などが特に高い事案は、この限りではないとのことでした。
もし“事故物件”と知らずに契約してしまったら…
契約した後で事故物件の事実を知った場合には、告知義務違反として損害賠償請求や契約の解除を求めることができるそうです。その場合、個人では分からないことも多いため、事故物件に関してトラブルになった場合は、迷わず弁護士に相談しましょうとのことでした。
当事者間で交渉するよりも、弁護士が関与することで、冷静に話し合いが進み、トラブルが早期に解決する可能性が高まるというメリットがあります。
万が一、事故物件でトラブルになった時には、弁護士法人・響までご相談ください。
tesou@nack5.co.jp までどうぞ!