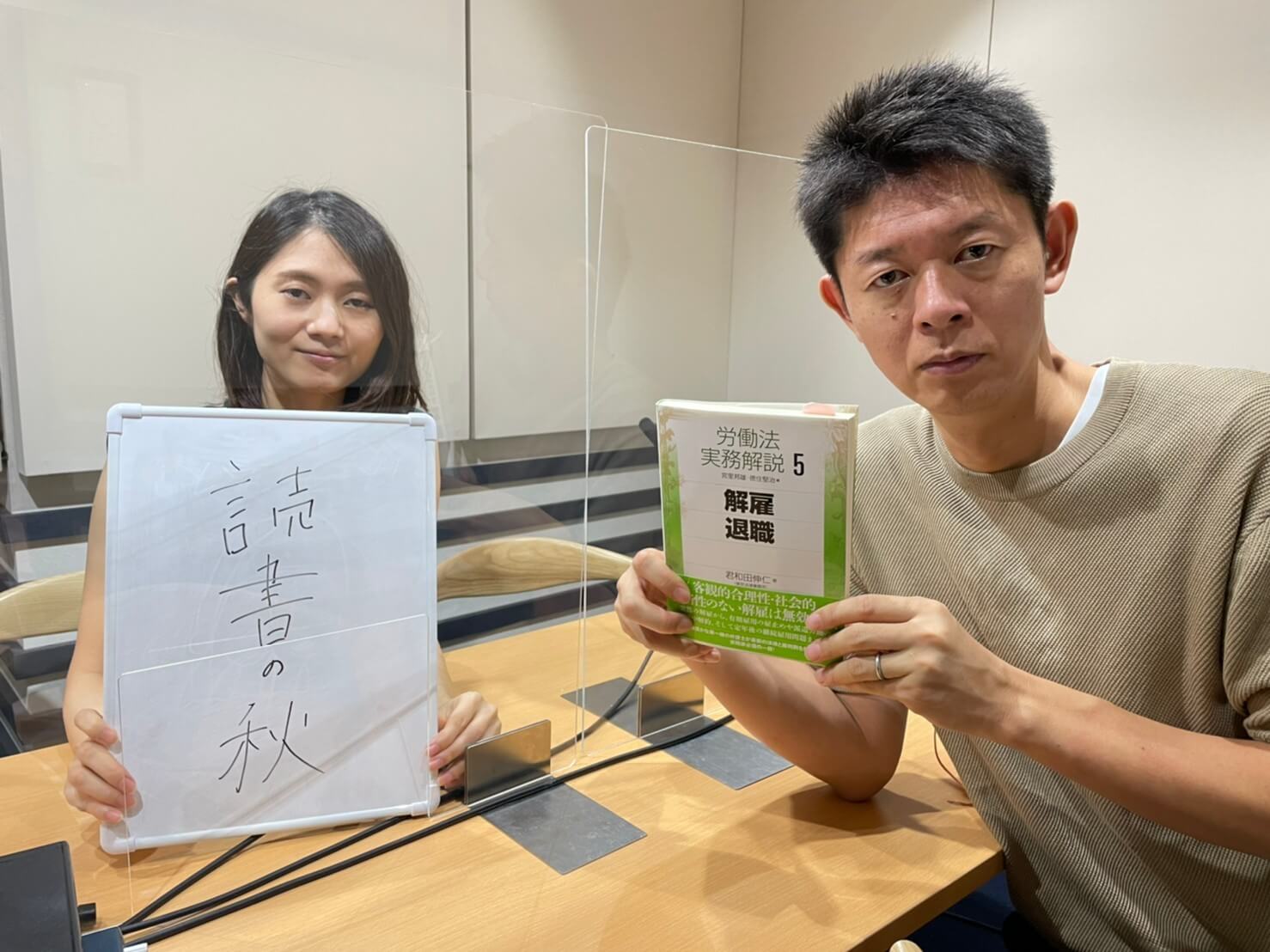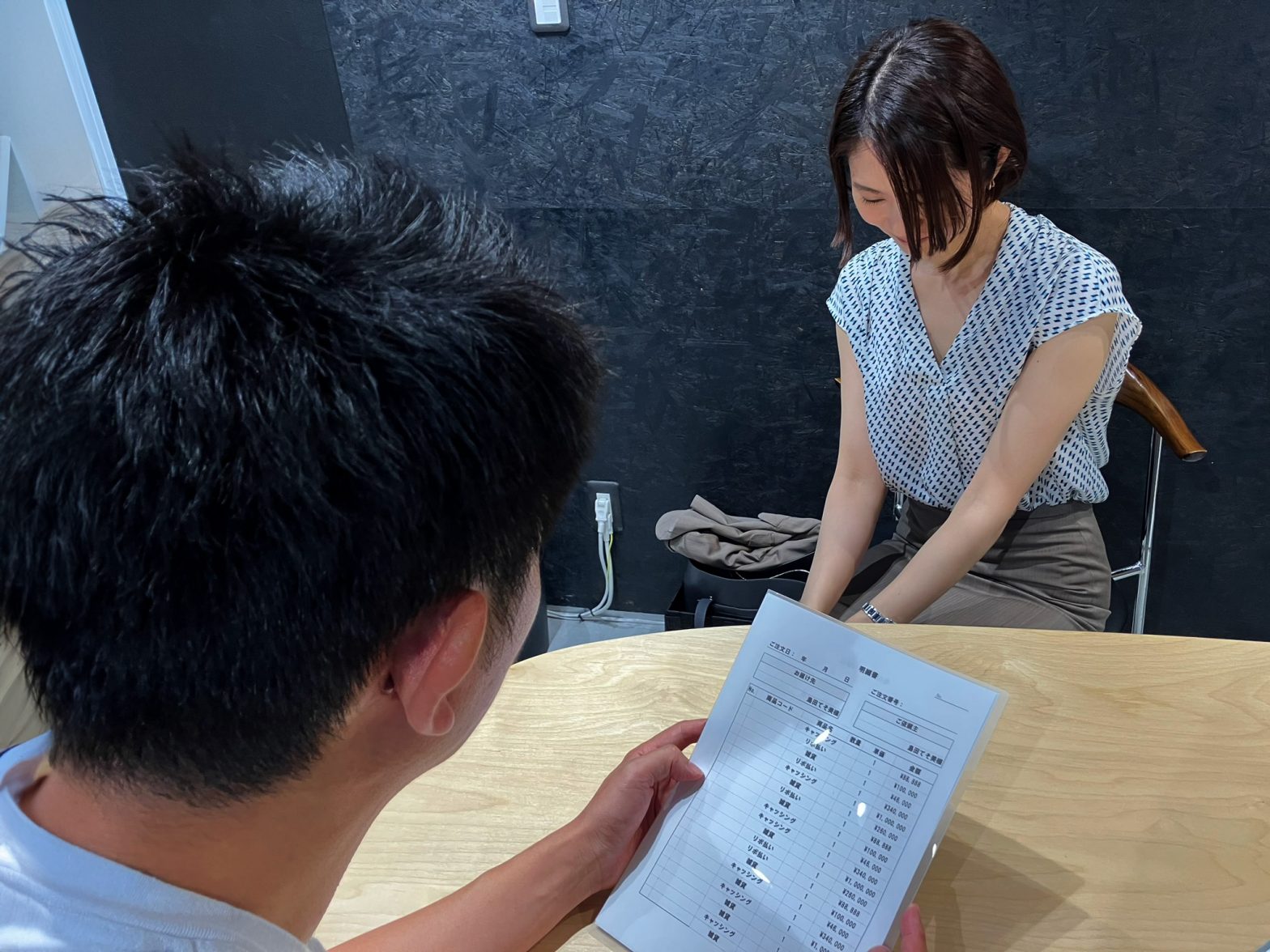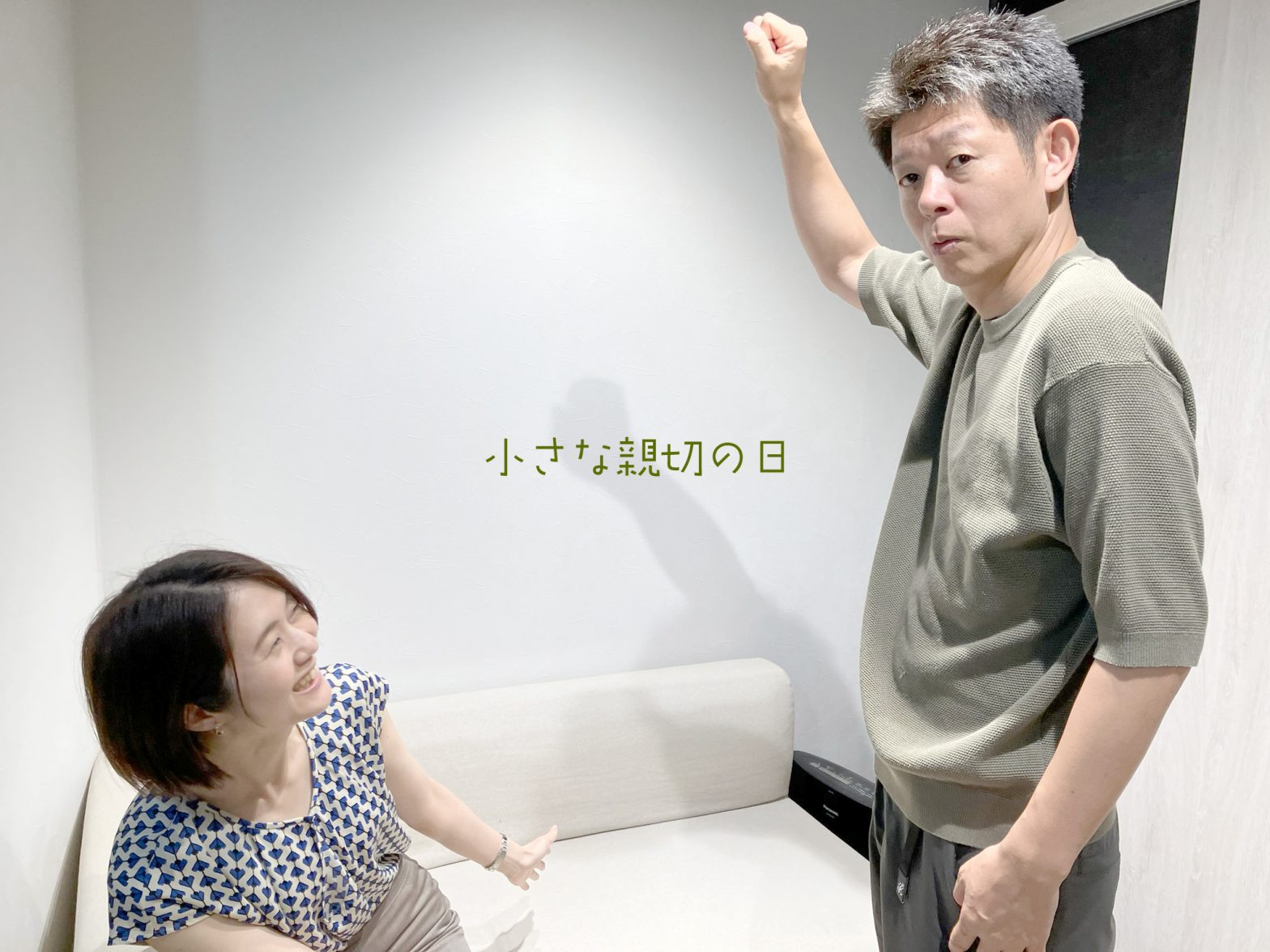今回も、弁護士法人・響の弁護士、古藤 由佳(ことう ゆか)先生にお越しいただきました!
放送日の9月23日は秋分の日。残暑はあるものの、もうすっかり秋ですね。
○○の秋、とよく言いますが、古藤先生にとっては読書の秋だそう!
愛読書を問う島田さんに、「六法全書ということで」とにこやかな古藤先生。
まさに法律家!なお答えお見事でした!!
さて、今年7月、ホビー誌を発行するホビージャパン社は、SNS上で転売行為や買い占め行為を容認するような発言をした同社の編集者を退職処分にしたと発表しました。
また同じく7月、ウェブメディア「&GP」で業務委託をしている編集者が、個人のSNSアカウントで人権侵害を伴う投稿をしていたとして、その編集者との契約を解除したと発表しました。
SNSは個人の考えを自由に発信できる場所ですが、大きな問題に発展すると、勤め先への批判など個人の発言では済まないレベルになってしまうこともあります。
そこで、第138回は、「個人の主張でもNG?SNSの発信が解雇につながるかも!?」というテーマで、古藤先生に解説していただきました。
SNS上での発言は、本来個人の自由ですが、それが会社の名誉や信用を毀損するような場合には、懲戒処分の対象となる場合があるとのことです。
ただし、どんなに重い処分でも自由にできるわけではありません。
特に、懲戒解雇や諭旨退職のような、雇用を失わせる処分については、対象社員をそれ以上雇用しておくことができないほど、重大な企業秩序違反が認められる必要があります。
ここで言う「諭旨退職」とは、懲戒処分の中で最も重い「懲戒解雇」(会社が強制的に従業員を退職させること)に相当するような不祥事や非行が従業員にあった際、本人に反省が見られるなどの理由から、まずは従業員の自主退職を勧告し、受け入れられなかった場合に解雇することを言います。今回のホビージャパン社の件も、「解雇」ではなく「退職処分」となっていることから「諭旨退職」であった可能性が高いとのことです。
ただし、諭旨退職は法律上定められている制度ではないため、その判断基準は会社によって異なります。各会社の就業規則には、諭旨退職の要件やルールが明記されていて、それに基づいて判断されることになります。
就業規則は必ず全社員が目にできるところに収められているので、自分の会社の就業規則がどこにあるのかも、ぜひ確かめてみてくださいね。
ちなみに、懲戒解雇の場合退職金は出ませんが、諭旨退職の場合、会社によっては退職金がもらえることもあるようです。また、失業保険については、離職前の2年間のうち、雇用保険に加入していた期間が通算12か月以上あれば、失業保険を受け取ることができます。
諭旨退職は、形式的には労働者自らが退職届を提出することになり、雇用保険法上は自己都合退職の扱いになります。そのため、7日間の待機期間に加えて、失業保険を受け取るまでには2か月ほどかかることになります。
また、退職後に転職を考えている場合、通常、前職での退職理由を積極的に申告する義務はありませんが、処分について事実上広く知られてしまっている場合には、影響が出る可能性もあります。
転職活動において、懲戒解雇されたことを積極的に申告する必要はありませんが、退職理由を聞かれて嘘の申告をした場合には、経歴詐称ということになります。経歴詐称が必ずしも転職先での解雇事由になるものではありませんが、その経歴詐称が「業務に著しい影響を与える」ものであった場合には、解雇事由になることもあります。
そもそも、面接時に嘘をついても、前職に前歴照会をされるとすぐにばれてしまいますね。
もしも、会社の処分にどうしても納得がいかない場合には、可能であれば、どんなに強制されても絶対に退職届を提出しないことが一番理想的とのことです。もし、すでに退職届を提出してしまった場合には、速やかに撤回する必要がありますが、仮に撤回できず、自己都合退職になったことで退職金が減額されたなど金額的な損害があった場合、損害賠償請求訴訟を提起することなども考えられるとのことです。
SNSは、個人の発言を自由に発信できる場所ではありますが、場合によっては会社をクビになったり、将来に大きく影響することもあります。あくまでも公共への発信であるということをしっかり意識して、上手にSNSと付き合っていきたいですね。