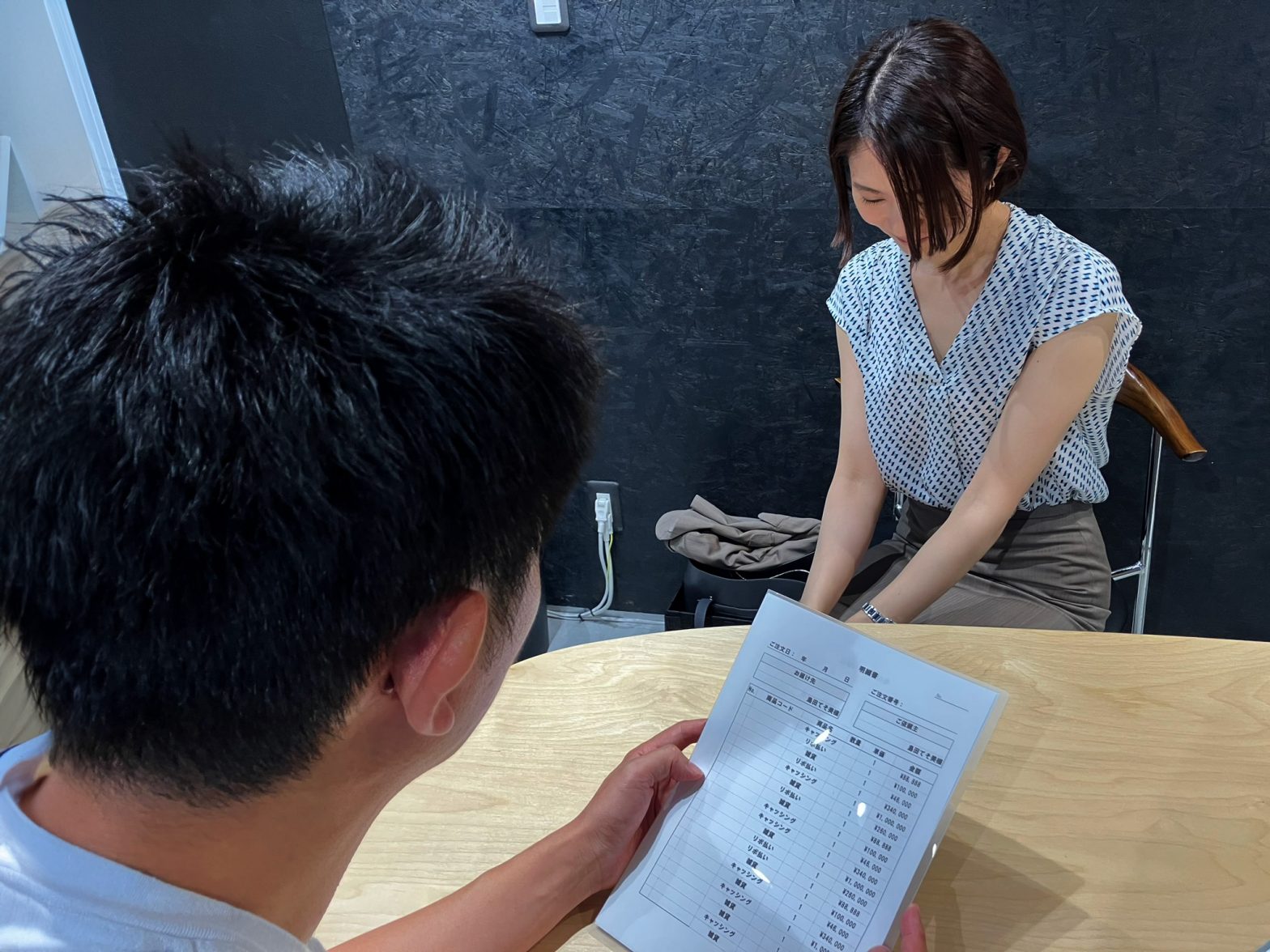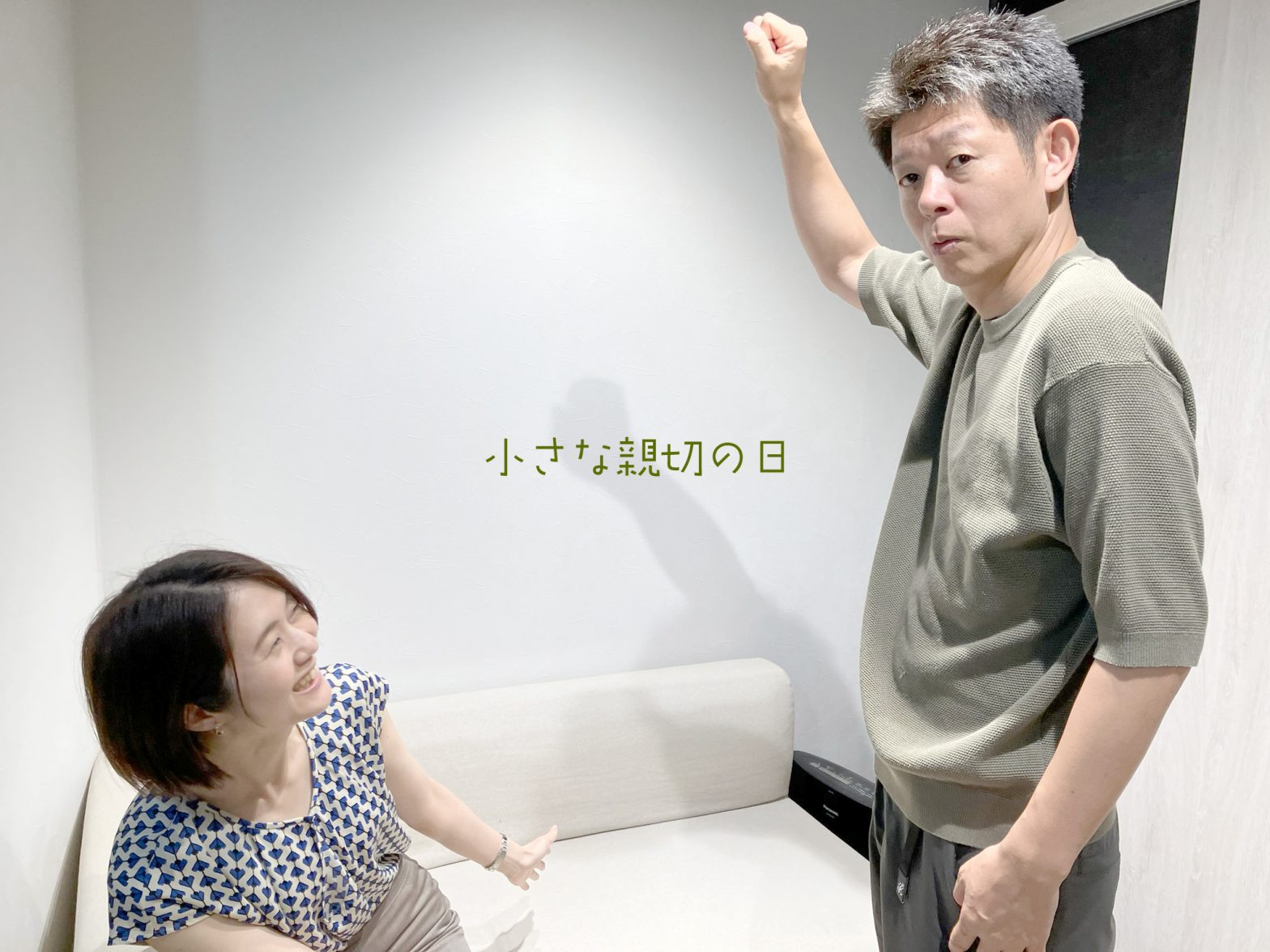放送日はCMソングの日でしたが、古藤先生も島田さんも、「タケモトピアノ」や「リゲイン」、「サントリーウイスキー」や「カローラII」など印象に残っているCMソングがたくさんあるようです。何度も繰り返し聞くCMソングは、気付いた時にはふと口ずさんでしまえるほど記憶に残っていたりしますよね!ブログをご覧の皆さまの記憶に残るCMソングは何でしょうか?
さて、長い夏休みは終わってしまいましたが、学生時代、夏休みに図書館で勉強した経験がある方は少なくないのではないでしょうか。これから訪れる読書の秋に利用を考えている方もいらっしゃるかもしれません。子どもから大人まで多くの人が利用する街の図書館ですが、実は「本の未返却」が長年大きな問題になっているそうです。第240回の放送では、「図書館の本の未返却」について、古藤先生に詳しく解説していただきました。
図書館の未返却本の実態は?
ネットやSNSでは、時折「学生時代に図書館で借りた本が出てきた」というような投稿がみられるようです。借りた本を意図せず紛失してしまうケースもありますが、夏休みの宿題のために本を借りたけれど暫く返していない、というようなケースも少なくありません。返さない方は軽い気持ちかもしれませんが、本が返却されないことは、図書館にとっては大きな問題です。
2016年、東京都足立区は長期未返却の本について「返還請求権」を放棄しました。10年以上返却されなかった本などが対象で、その数約1万9千冊。被害総額は約2500万円に上り、中には、2万円以上する本も7冊含まれていたそうです。さらに2017年度にも、足立区は約2千冊の本について返還請求権を放棄しました。放棄した理由は、督促はがきを送るための費用や手間に対してその効果が薄かったためだそうです。新宿区では、11の区立図書館における数千冊の未返却本のうち、貴重な書籍や他の自治体から借りた本について職員が直接訪問して返却を求めましたが、2016年度に回収できたのは19冊程度だったそうです。こうした状況は、全国の図書館でも同様にみられます。
督促に要する費用に関して見ると、埼玉県川口市が2016年度に送った約1万7千枚の督促状にかかった費用は約84万円。過去5年間では500万円にも上るそうです。
そんな中、未返却本の返還請求権を放棄することは、図書館にとって苦渋の決断でもあります。
公立図書館の運営費用は税金で賄われているため、本の返却を求めて利用者を訪問したり、督促状を送るのにかかる費用や、返却されなかった場合に新たに本を購入する費用も、当然全て税金です。つまり、本の未返却は「税金の無駄遣い」にも繋がっています。
図書館の本を返さないと犯罪?
古藤先生によると、図書館法では「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価も徴収してはならない」とされているため、延滞料や罰金の導入は難しいそうです。そのため、公立図書館では、未返却者に対して督促状を送ったり、延滞・未返却に対して貸出期間の制限や貸出禁止などのペナルティを科したりすることで対応しています。
しかし、罰金や延滞料が科されないからと言って、本の未返却が罪に問われないわけではありません。やむを得ない事情で返せないのではなく、返すつもりがなくそのまま本を持っていた場合は「横領罪」にあたり、図書館が被害届などを提出することもできるそうです。
「横領罪」と聞くと、会社のお金を勝手に使うなどのイメージを持っている方が多いかもしれませんが、「横領」とは“自分の占有下にある財物(自分が預かっている他人の物・自分が他者から預かっているもの)を自分のものにしてしまうこと”をいうため、お金以外のものでも「横領罪」は成立するそうです。
「返す意思があったかどうか」が判断基準となりますが、例えば、何度も督促されているにもかかわらず意図的に無視していた場合は、「自分の物にしようとする意思がある」とされ、単純横領罪が成立する可能性が高くなるそうです。ただ忘れていただけですぐに返却した場合は、横領罪には該当しません。ただし、横領罪に該当する・しないにかかわらず、民事上は、返却までに図書館側に発生した損害を賠償する責任を負う可能性があるそうです。
“人のものでも、何年も持っていれば自分のものになる”というような話を聞いたことがある人もいるかもしれません。古藤先生によると、確かに時効の中には「取得時効」といって、時効期間を満了する事でその物の所有権を取得できる制度があるそうです。「取得時効」が成立するには「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有する」という要件を満たす必要があります。
しかし、そもそも図書館から本を借りる行為は、図書館に「所有権」がある事を前提とした使用貸借契約です。つまり、何十年占有の状態で経過したとしても、借りた人に「借りているという認識」がある以上、本の所有権はずっと図書館にある状態になります。そのため、何年経とうとも「取得時効」は成立しないそうです。
図書館の本を返さないことは、刑事・民事とも責任を問われる可能性がありますが、実際のところ1冊、2冊を返さないで被害届を出されたり裁判を起こされたケースは、古藤先生も聞いたことがないとのこと。
確かに返さない人を一人一人訴えていたらキリがないですし、それこそ費用もバカになりませんよね。そのため、図書館の本の未返却は、より解決の難しい問題となっているようです。
とはいえ、公立の図書館は税金で成り立っています。もし図書館から借りたままの本があるという方は何年前のものであっても、必ず返却するようにしましょう。図書館の本は公共の財産であるということを忘れずに、図書館のルールは守るようにしたいですね。