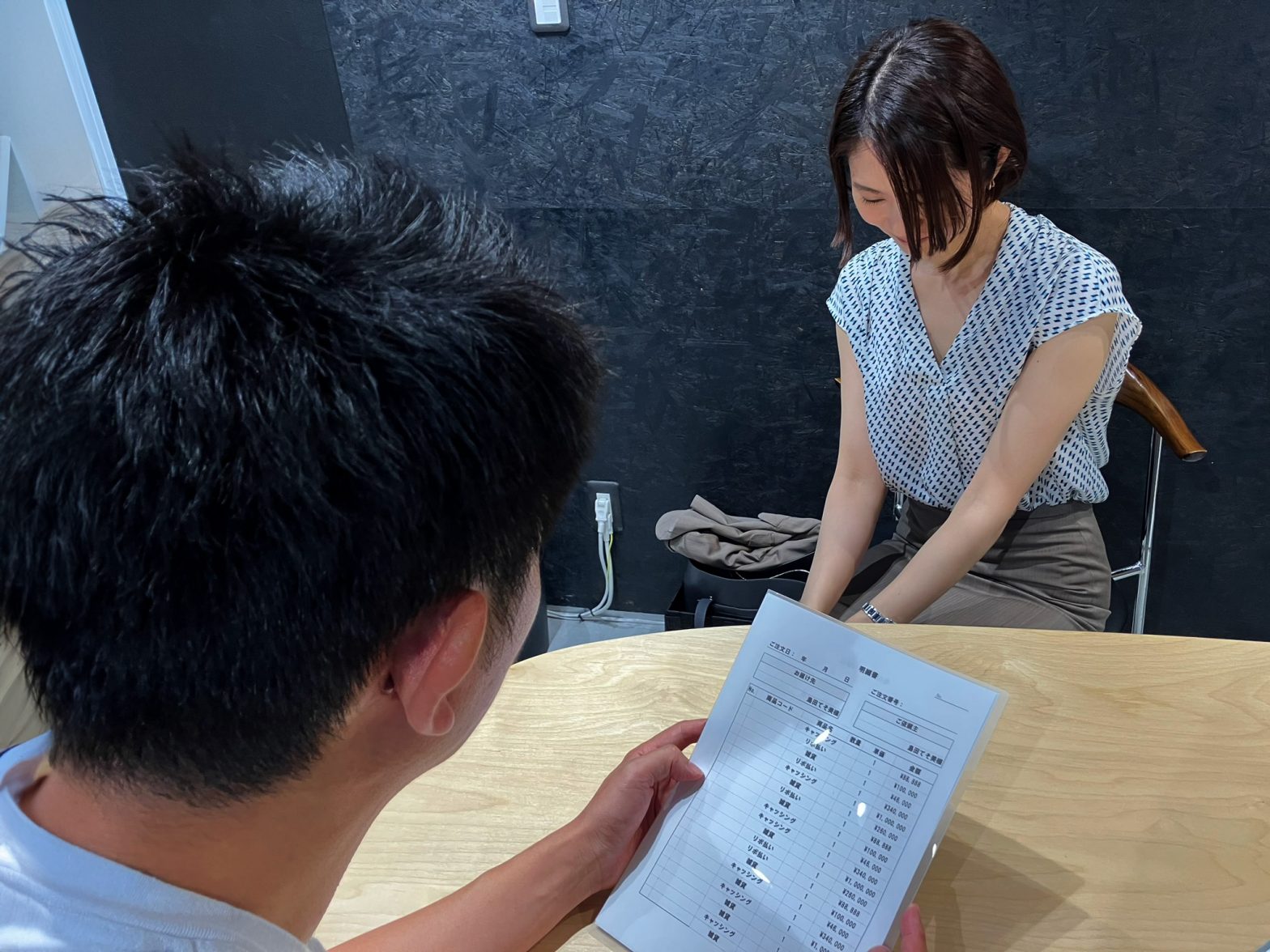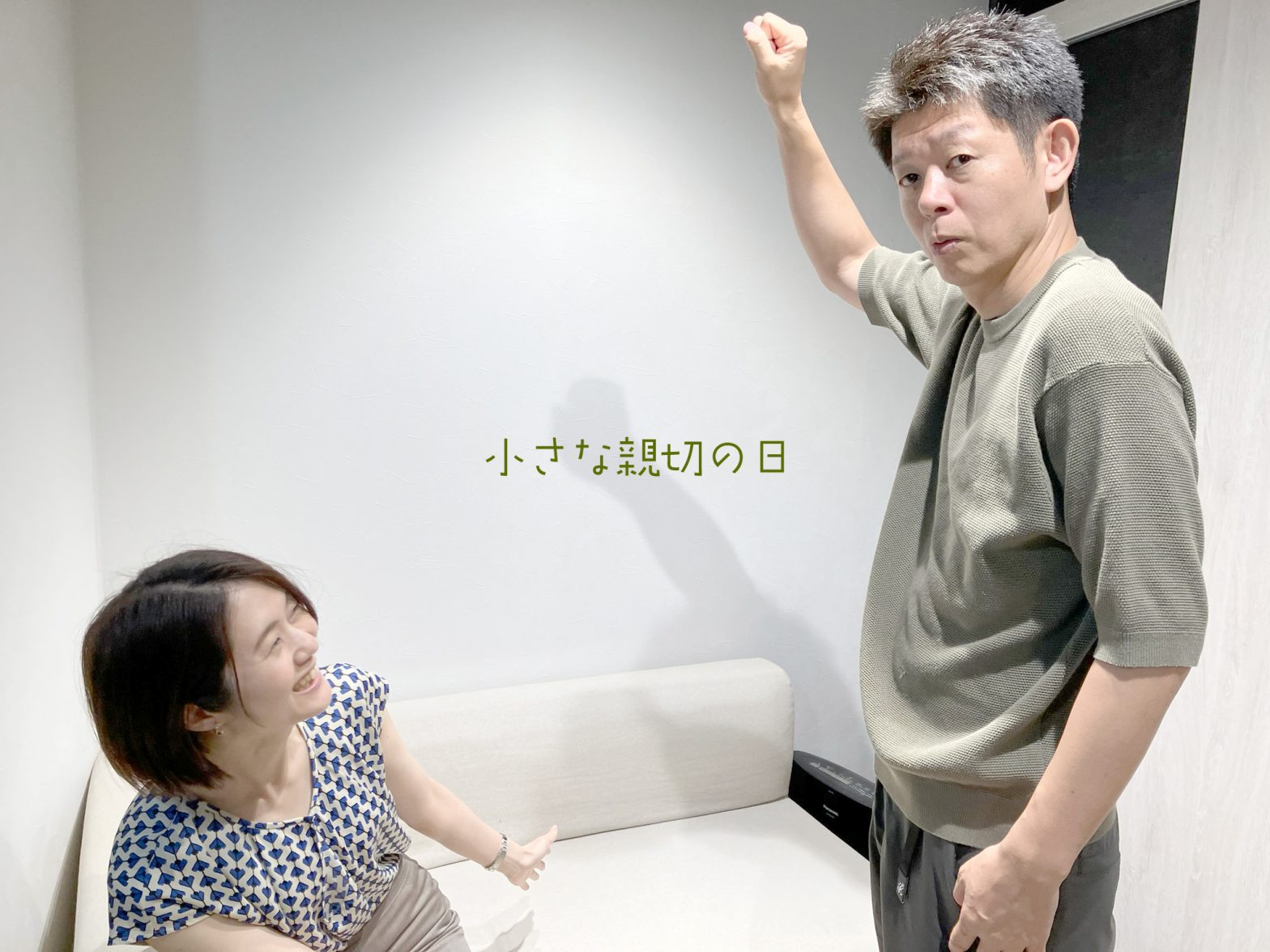3月3日は桃の節句。ひなまつりですね。古藤先生は二人姉妹ということで、幼い頃は素敵な雛人形を飾ってもらっていたそうです!島田さんも、昨年末に女の子が生まれ、今年は初節句。義実家から素敵な雛人形をいただいたのだとか。ただ、マンション暮らしということで、お内裏様とお雛様だけを寝室に飾っているそうなのですが、目が覚めると、15cmくらいの場所にバーン!とお人形があって、深夜だとちょっと怖いそうですよ(笑)
とはいえ、女の子の幸せを願うひなまつり、素敵な風習ですよね。
子どもに勝ってに課金された!相談が増加
さて、スマホのアプリを使った配信ライブなどで今や欠かせない機能となっているのが、「投げ銭」です。配信者に対して、応援する視聴者がお金を送るシステムで、サービスによって名称が違い、例えばYouTubeだと「スーパーチャット(スパチャ)」と言ったりしますね。実際に投げ銭をしたことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか?「投げ銭」の利用者は増加していて、市場規模は500億円に達するとも言われています。
ところがその一方で、国民生活センターには、「中学生が親のクレジットカードを勝手に使い、100万円以上の請求が来た」などの相談が寄せられるなど、子どもたちがオンラインゲームやライブ配信アプリに没頭し、課金額が膨れ上がるケースが急増しており、注意を呼び掛けています。古藤先生によると、弁護士法人・響にも、「ゲームで使いすぎてしまって思いがけない高額請求が来た」という相談が寄せられることがあるそうです。いきなり身に覚えのない高額請求が来たらびっくりしますよね。
そこで第161回の放送では、「子どもが勝手に課金してしまったアプリ代金は返してもらえる?」というテーマで古藤先生に詳しく伺いました。
投げ銭(課金)は返金してもらえる?
古藤先生によると、成人が行った投げ銭については、当然返金してもらうことは出来ませんが、未成年に関しては「未成年者取消権」というものがあるそうです。これは、親の同意を得ずに課金・投げ銭をした場合、民法第5条に基づいて、親の同意を得ていないことを理由に契約を取り消すことができるという権利です。
ただし、「未成年者取消権」が認められるには、次の2つの条件を両方満たしている必要があるそうです。
1つ目の条件は「未成年者が年齢を偽るために詐欺的な行為をしていない」ことです。
未成年者が、事業者側に成人していると信じさせるために、積極的に行動した場合(極端な例でいえば、身分証を偽るなどの行為)がある場合には、未成年者側の要保護性が下がるため、取消権を使えなくなるそうです。
2つ目の条件は「保護者が課金を一切認めていない」ことです。
保護者が「少しくらいなら課金していいよ」など、課金自体に反対していなかった場合、課金に了承しているとみなされるため、取り消しはできないそうです。お小遣いの範囲内で取引をしたとみなされる場合、その部分については”親が子の自由な処分を認めた”と判断されるためだそうです。ただし、例えば「1000円までなら」というように、具体的な金額を伝えていた場合、その金額を超えた分については返金してもらえる可能性があるそうです。
子どもの無断課金を返金してもらう方法は?
もし、先述の2つの条件を満たしていて、返金してもらえる可能性がある場合の対処法についても伺いました。
まずは、アプリのダウンロード元である、App StoreやGoogle Playなどのストアのホームページから返金申請をします。ストア側で審査を行い申請が通れば、返金を受けられる可能性があるそうです。ただし、ストア側では判断できず、返金はできないという回答になるケースもあるとのことでした。
次に、カード会社にも状況を伝えます。これにより、対象の支払いを少し待ってもらえる場合があるそうです。ただし、ストア側から返金ができるかどうかの判断が出ない限り、カード会社としては請求するのが一般的とのことでした。
ただし、クレジットカード契約には「善管注意義務」というものがあり、クレジットカードをきちんと管理しないことが原因で他人に使われた場合、名義人が支払わなくてはならないという決まりがあるそうです。家族など、”本人以外でも利用できる状態だった”場合は管理不十分とみなされるため、実際には、クレジットカード会社から返金が認められるケースは滅多にないと考えておいたほうが良いとのことでした。
子どもの無断課金を防ぐ方法!
古藤先生によると、未成年が勝手にやったことであっても、返金を受けるには条件があり、実際に返金が認められるケースは稀とのことでした。「未成年者による課金は返金が受けられる」と思っていた方も多いかもしれませんが、返金を受けられることはほとんどないと思って対策をした方が良いようです。
そこで、子どもが勝手に課金しないようにする対処法についても伺いました。
1つ目は、スマホを「ペアレンタルコントロール設定にする」ことだそうです。子ども用のスマホがある場合には、「ペアレンタルコントロール」を設定すると、保護者の承認がないとアプリのダウンロードやアプリ内での課金が出来ないよう、制限をかけることができるそうです。
2つ目は、「子どものスマホにクレジットカード情報を登録しない」ことだそうです。スマホは一度端末にクレジットカード情報を入力すると、自動保存されるのが一般的です。もし入力した場合には、登録せずに、毎回入力するように設定することが大切とのことでした。
「子どもが勝手にクレジットカードを使えない状況にしておく」ことが大事なんですね!もし、子どもの無断課金で高額請求が来てしまった場合には、お早めに弁護士にご相談ください!
お困りの際には、弁護士法人・響まで!