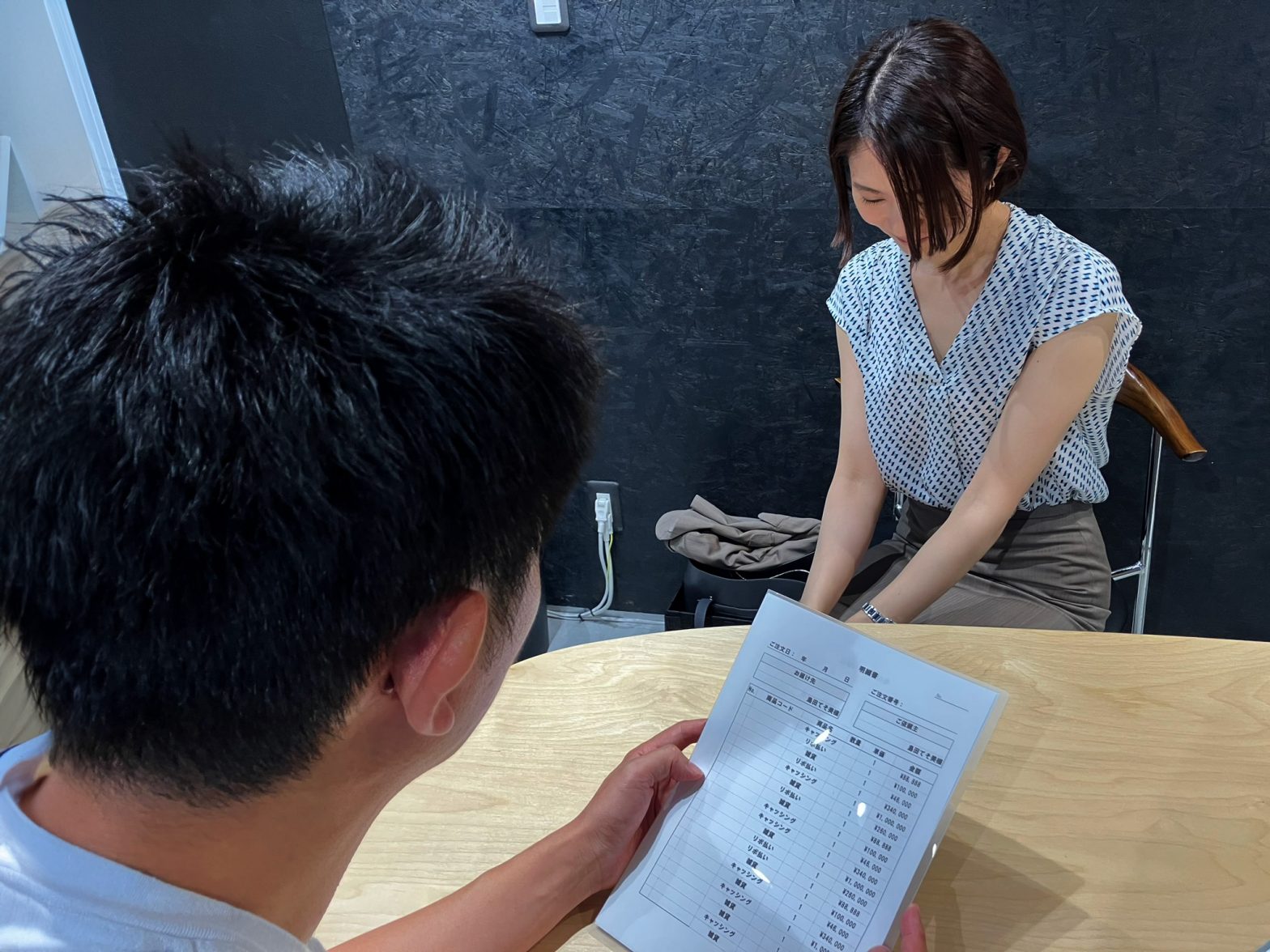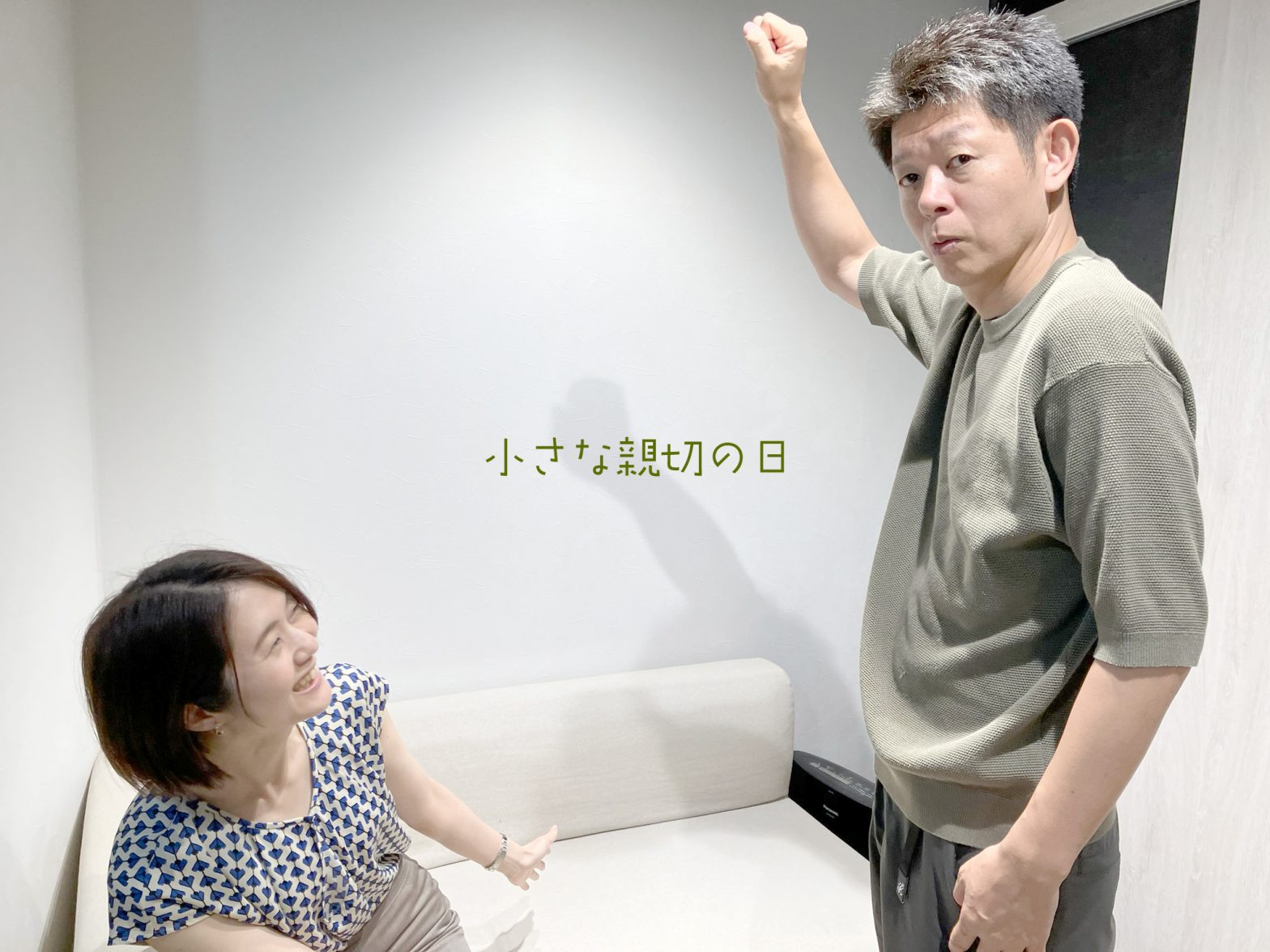卒業シーズンですね!このブログをご覧の皆様もきっと素敵な卒業式の思い出があることと思います!
今年卒業される学生さん、ご家族の皆様、本当におめでとうございます!
ちなみに、古藤先生にも卒業したいのがあるそうで、それが「深夜の間食」だそうです。帰宅後ご飯も食べずに寝てしまうと、深夜にお腹が空いて目が覚めることがありますよね。そんな時、我慢しきれずに食べてしまうのが「納豆ご飯」なのだとか。島田さんからは「深夜に納豆ご飯作るの結構面倒くさくない!?」とツッコミが入っていましたが、健康的な夜食ですし卒業しなくても良いかもしれませんね(笑)
皆さまは、卒業したいと思うものがありますか?
さて、今年に入り、「駆け込み生前贈与が増えるかも」「生前贈与は年内にしたほうがいい」「生前贈与は今後どうすればいい?」など、生前贈与に関して様々な声が上がっています。これは、2022年末に公表された「令和5年度 税制改正大綱」に、生前贈与に関する変更が盛り込まれたためだそうです。「税制改正大綱」とは、各省庁や各種団体からから上がってくる税制改正の要望などを取りまとめて、翌年度以降の税制改正の方針をまとめたもので、今後の税制改正の基礎になるものです。
では、生前贈与に関する税制の何が変わるのでしょうか。
第215回の放送では、「生前贈与に関する税制の変更点」について、古藤先生に詳しく解説していただきました。
生前贈与って何?方法やメリットは?
古藤先生によると、「生前贈与」とは、文字通り、“生きている間に第三者に財産の贈与を行っておくこと”だそうです。生前贈与を行うと、相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減することができます。
生きている間に財産を贈与した場合、「相続税」より税率が高い「贈与税」が発生しますが、贈与税には年間110万円の基礎控除額があります。そのため、年間110万円以内であれば、非課税で財産を移転することができるそうです。子どもや孫に対して、この贈与を毎年繰り返していくことで、将来的な節税対策になるんですね。
また、生前贈与を行うことは、相続人同士のトラブルを防げるというメリットもあるそうです。相続財産がある場合、例えば、どの財産を誰がどれくらい受け取るのか、遺言書の解釈、本人の意思が本当にあったのかなどで相続トラブルになることがあるそうです。
ですが、生前贈与の場合、贈与する人が家族などの関係者に直接贈与することができます。そのため、贈与する人の意思を誤解される可能性が低くなるそうです。
ただし、生前贈与には注意点もあるとのこと。
死期が迫った人が相続税を回避するために急遽財産を贈与することは明らかに相続税逃れであるため、“贈与者が亡くなる日から遡って3年間になされた生前贈与は相続財産に加算する”という「生前贈与加算」のルールがあるそうです。
この「3年ルール」がありますが、それでも、生前贈与はその方法やメリットがわかりやすいことから、相続税の節税対策では定番とされてきたそうです。
生前贈与加算の変更…対策は?
2022年に公開された令和5年度の税制改正大綱には、「相続財産に加算される生前贈与の加算期間が変更される」という内容が盛り込まれたそうです。
先述の通り、これまで「生前贈与加算」の期間は3年でしたが、今回の改正で、その期間が「3年」から「7年」に延長されることになるそうです。
たった4年と思われるかもしれませんが、相続税対策を考える時というのはそれなりに高齢になっていますよね。仮に80歳で亡くなると仮定して考えてみると、生前贈与加算が7年になることで、73歳以降の贈与は相続財産に組み込まれることになります。つまり、節税を考えると73歳より前に生前贈与を済ませておかなくてはならないということになります。
毎年、非課税で贈与出来る限度額の110万円を生前贈与したとしても、10年間で1人当たり1,100万円までしか贈与することはできません。相続税対策を考える人は、ある程度大きな財産がある人でしょうから、相当早い年齢から始めなければならなくなってしまいます。
これで事実上、生前贈与による相続税対策は封じられたともいえるのだそうです。
この生前贈与加算の期間延長は、来年2024年(令和6年)の1月1日から適用されるそうです。
そのため、今年(2023年)は駆け込み贈与が増えると予想されているとのこと。
2023年中に生前贈与をした財産は、2027年以降に相続が発生した場合には、相続財産に組み込まれないそうです。そのため、何も対策をしなければ相続税が発生する可能性が高いという人は、2023年中に生前贈与しておいた方が良いとのことでした。
特に子どもや孫が多い場合、人数×110万円の生前贈与ができますから、年内に生前贈与を行うことで、大きな節税対策となり得ますよね。
ただ、古藤先生は「生前贈与を非課税の範囲で行うには、専門知識が必要なため、税理士または弁護士など専門家への相談をお勧めします」と仰っていました。
非課税で贈与を行うことが目的であれば税理士、揉める可能性がある場合や、不動産の権利関係などが複雑である場合は弁護士への相談がお勧めだそうです。
生前贈与や相続について、困った時には、ぜひ弁護士法人・響までご相談ください!