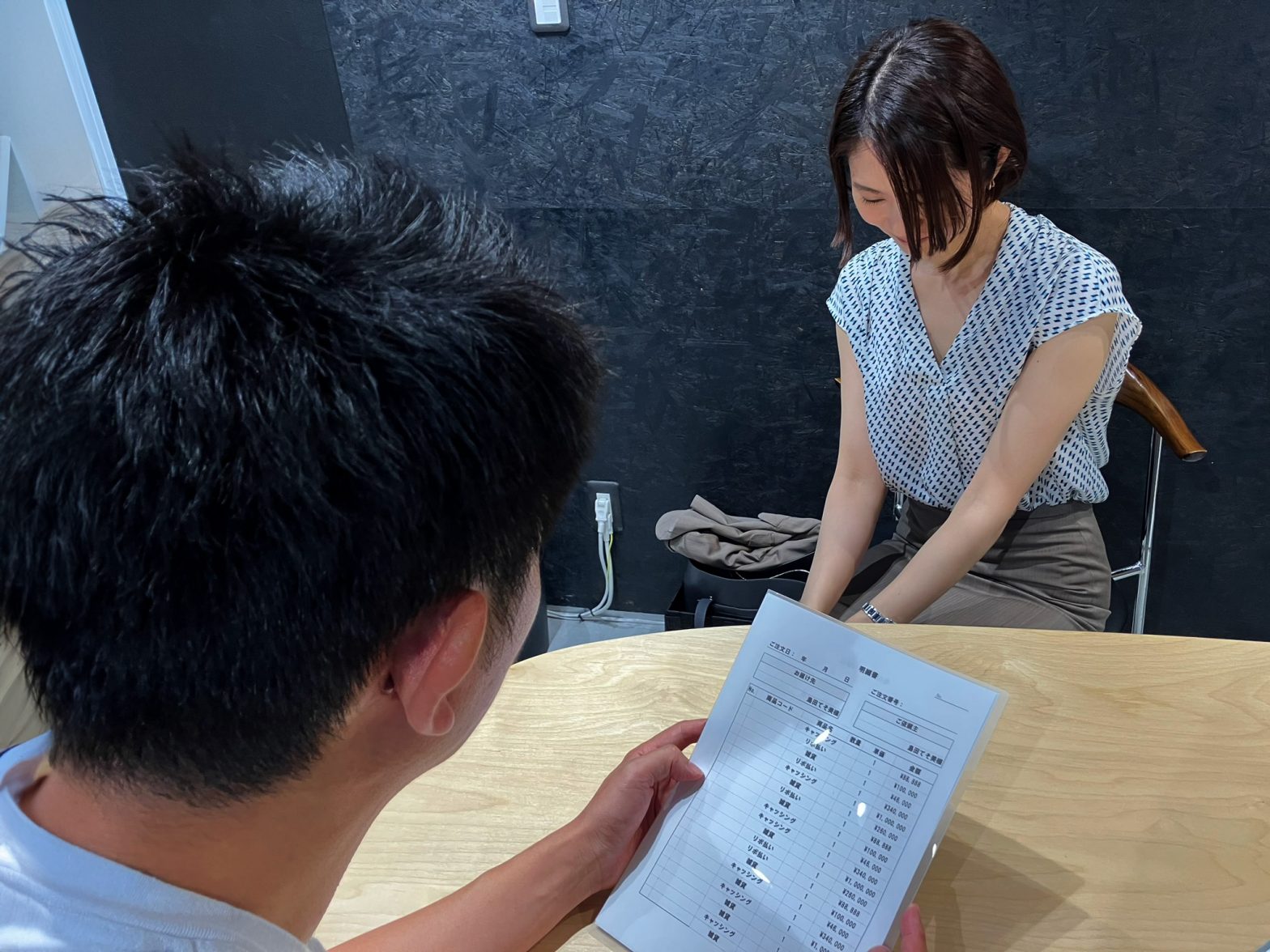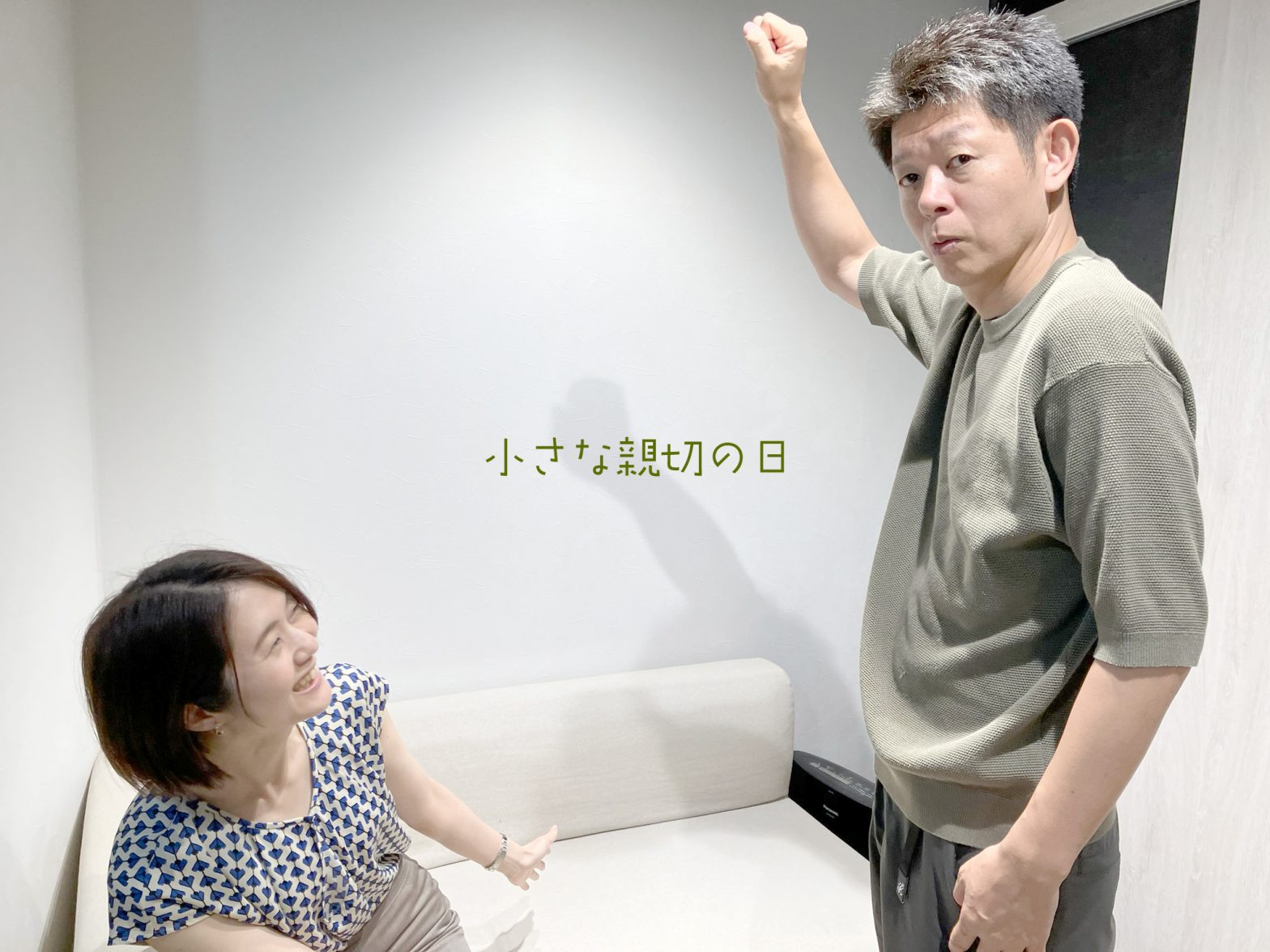10月に入り、季節はすっかり秋…ということで、今回は、衣替えのお話から始まりました。
秋物を着始めたという方も多くいらっしゃるかと思いますが、そろそろ冬に向け、夏物をしまい冬物を出すといった、本格的な衣替えをしていきたいですね。
さて、第八十八回目は「相続税の債務控除制度」をテーマに、借金や未払い金と言ったマイナスの財産がある場合の対処法や、知っておくべき相続税の控除など、事前に気を付けておくべきことについて、坂口先生に詳しく教えていただきました!
相続では、財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も対象になります。
マイナスの財産がある場合には、「相続放棄」をしてしまう手もあるのですが、相続放棄をすると、プラスの財産も放棄することになってしまうそうです。
相続財産の中にマイナスの財産が含まれている場合でも、マイナスの財産の中には、「控除」できる財産があるので、そういった制度を利用することで、賢く相続財産を受け取ることができるかもしれません。
相続税が発生するのは、相続財産が3000万円を超える場合です。
3000万円には、土地や家などの評価額も含まれる為、一般的なご家庭でも超えてしまうことが多いそうです。
さて、今回のテーマでもある「相続税の債務控除制度」。相続により取得した財産から、債務の額を引いて、その残額に対して相続税がかかるという制度です。
借金や未払い金などの債務で、控除の対象となるものは、
✓亡くなった人が亡くなった時点で負っていること
✓支払い義務のある債務であること
とのことです。
具体的には、借金、医療費、公共料金や税金の未納分などです。
このほか、お通夜やお葬式の費用も対象となるのだそうです。
債務控除の対象とならないものは、団体信用生命保険(団信)付きの住宅ローン、保証債務(支払い義務が確実とは言えないため)などです。
また、葬儀関係費用の中でも、香典返し、初七日、四十九日の法要など、お葬式の後にかかる費用は対象外になります。
ここで気を付けたいのが、債務控除が利用できるのは、相続税を払う人全員ではないということです。相続人のうち法定相続人と、法定相続分のうち一定をすべて相続された人が利用できる制度になります。
特定の財産を遺贈された第三者「特定受遺者」は債務控除を受けることができません。
例えば、相続人が葬式費用を支払った場合には債務控除が利用できますが、特定受遺者は債務控除ができないのでご注意ください。
相続においてどんな制度があるのか・どんな控除が受けられるのか・自分が対象になるのかは、事前に知っておくことが大切です!
控除があることを知ったうえで、税理士さんなど専門家に、事前に相談しておくのがおすすめです。
坂口先生がいらっしゃる弁護士法人・響は、響グループとして税理士法人・響があり、連携対応も可能とのことですので、相続についてお困りの際にもぜひ、弁護士法人・響へご相談くださいね!