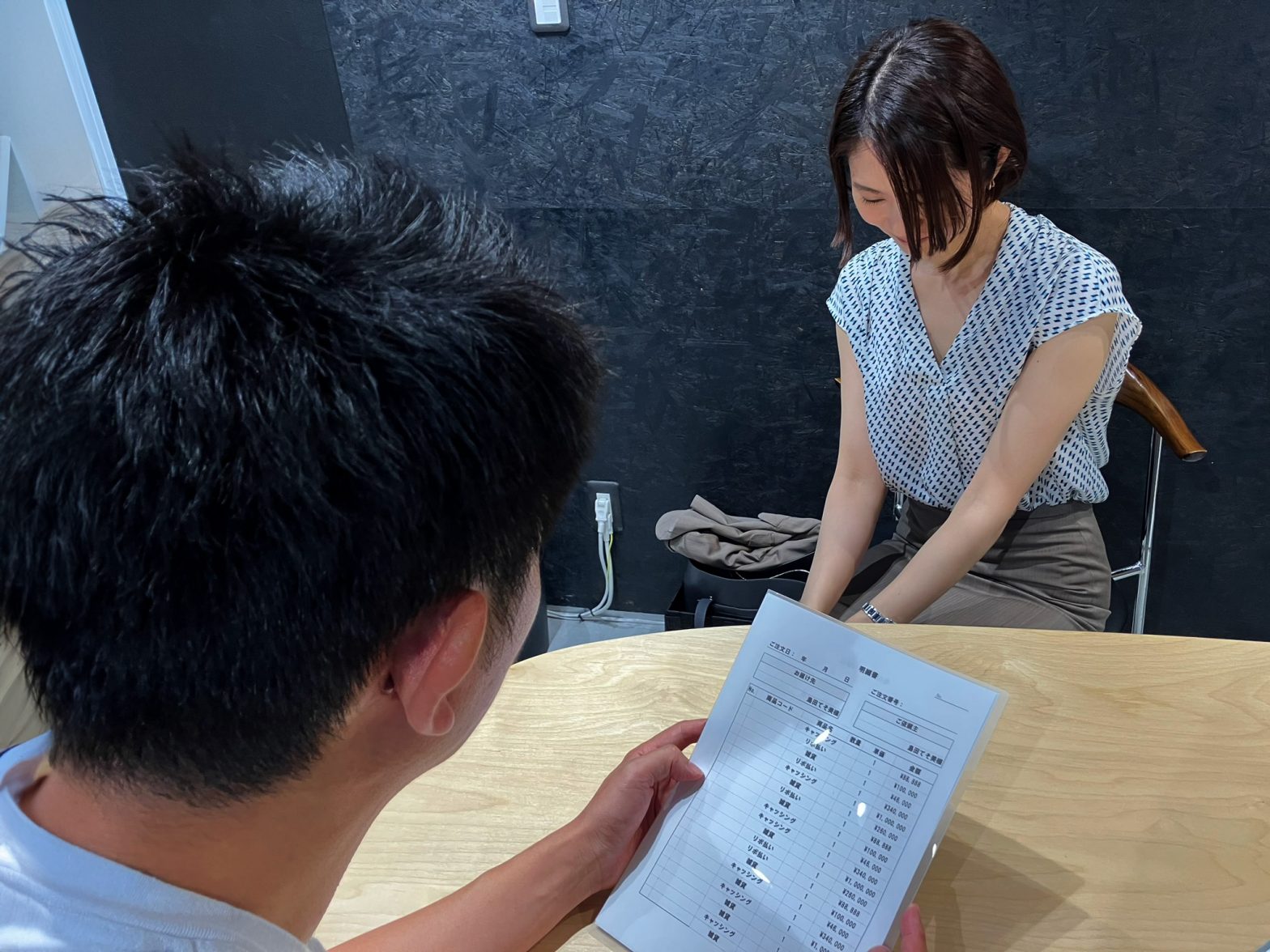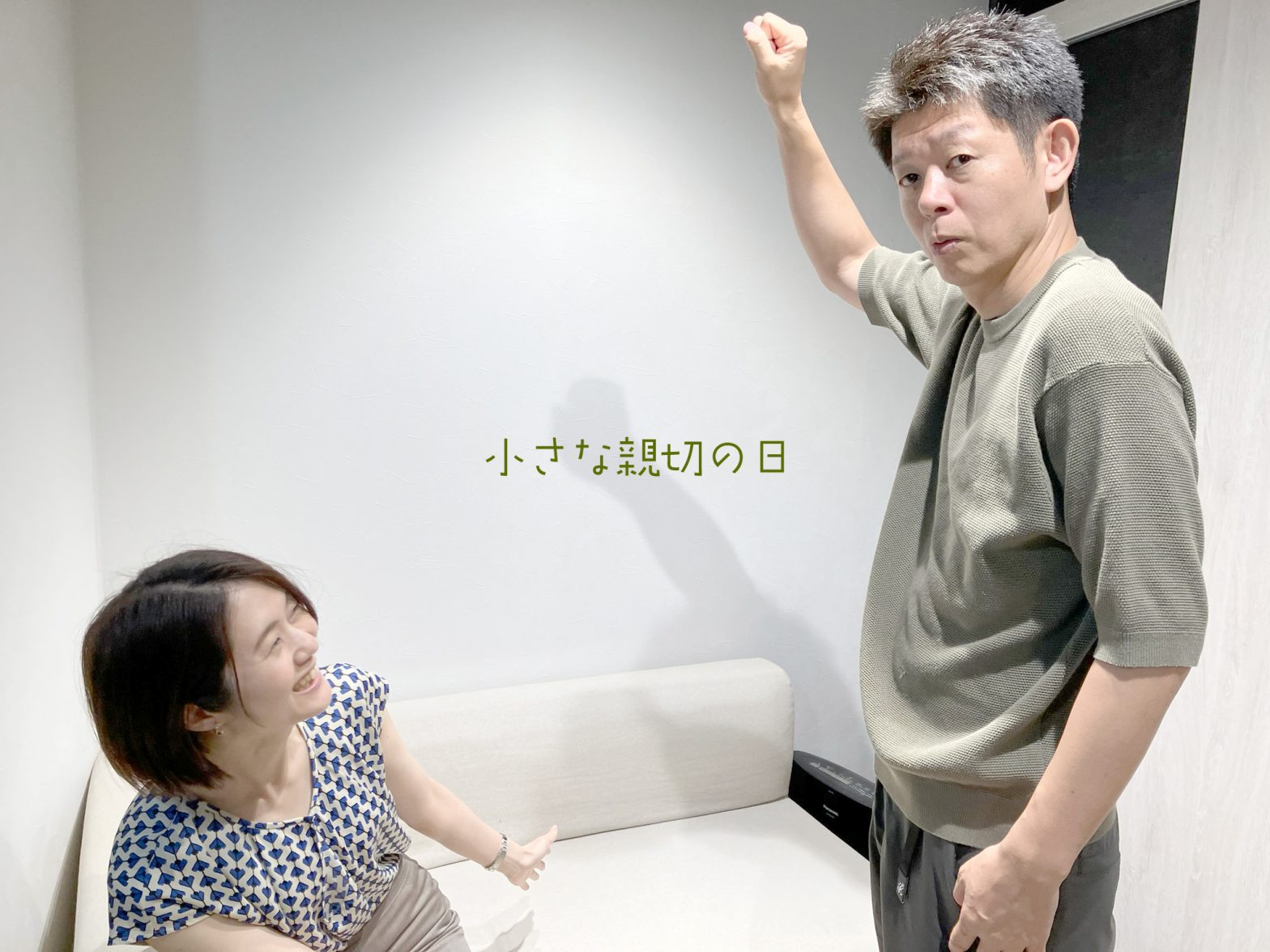放送日は語呂合わせで「いいいろ(1116)の日」でした。古藤先生は黄色がお好きとのことですが、島田さんによると来年、2024年のラッキーカラーは青と黄色だそうですよ!風水では黄色は金運が上がる色とも言われますし、古藤先生は2024年も素敵な年になりそうですね!
さて、自転車は道路交通法上、軽車両に分類されるため、車の一種と位置づけられていることはご存知の方も多いと思います。では、もし自転車同士の交通事故が起こった場合、対処やその後の処理は自動車と同じなのでしょうか?ここ数年、自転車事故は増加傾向にあると言われていますので、万が一に備えて、どのように対処すべきか知っておくことも重要です。そこで、第250回の放送では、自転車事故に遭ってしまった時に役立つ知識を古藤先生に詳しく解説していただきました。
自転車同士での交通事故!自動車事故との事故対応の違いは?
古藤先生によると、自転車同士の交通事故でも、基本的には自動車事故と同じ対処をするとのことです。第一に「怪我人の救護と周囲の安全確保」、次に「警察への連絡」、そして「保険に加入していれば保険会社に連絡」をします。「怪我を負った場合は病院で治療を受け」、その後「損害賠償請求(示談・調停・訴訟)」という流れになります。
自転車同士の事故の場合、自動車事故ほど大きなものにはならないことが多いので、当事者同士で済ませてしまい、警察へ届出をしない人も少なくないとのことですが、自動車事故と同様、たとえ軽微な自転車事故であっても、警察への届け出は必ずしなくてはいけないそうです。
基本的には、自動車事故も自転車事故も同様の対処とのことでしたが、もちろん異なる点もあるそうです。その一つが保険加入の有無です。
自動車は自賠責保険への加入が法律上義務付けられているため、自動車事故の場合は、加害者が保険に加入しているケースがほとんどです。また、自動車に乗る人の多くは、自賠責保険に加えて、任意の自動車保険にも別途加入していることと思われます。しかし自転車の場合、自転車保険への加入を義務化する自治体は増加しているものの、今年行われたau損保の調査によれば、全国の加入率は63.5%と、まだ1/3以上の方が未加入だったそうです。
もし、加害者側が任意保険に入っていなければ、慰謝料は加害者に直接請求するしかありません。しかし、加害者側の財産が乏しい場合、請求しても支払いが期待できない、あるいは話し合いが難航するといった状況が想定されるとのこと。つまり、慰謝料の金額だけではなく、そもそも支払ってもらえるかどうかという問題が出てくることになります。
もし事故の加害者側が保険に入っていなかったら…!
自転車同士の事故で怪我をして、加害者側が保険に入っていなかった場合、どのような方法をとればいいのでしょうか?
古藤先生によると、対処法は3つあるそうです。
①自分が加入している保険を使う
自転車保険には、自身の怪我の治療に関する補償を受けることができるものがあるそうです。自転車保険に入っていない場合でも、加入している生命保険や医療保険、傷害保険、自動車保険、さらにクレジットカードの付帯保険によっては、自転車事故による怪我に関する補償が付いているものがあるとのこと。こ保険やカードの契約内容にもよりますので、まずはご自身の契約を確認してくださいとのことでした。
②TSマーク付帯保険を使う
TSマークは、自転車安全整備士の点検を受けた自転車に対して貼付されるもので、このマークが付いている自転車には「傷害保険」と「賠償責任保険」が付いているそうです。
TSマークには3種類あり、それぞれ賠償額の範囲が異なるとのこと。
・第一種TSマーク(青色):一律1万円
・第二種TSマーク(赤色):一律10万円
・第三種TSマーク(緑色):一律5万円(保険会社による示談交渉サービス付)
③労災保険を使う
通勤中や業務中に自転車事故で怪我を負った場合は「労災保険」が使えるとのことです。その怪我について労災保険法上の「通勤災害」あるいは「業務災害」として認定されれば、療養補償や休業補償、障害給付などが受け取れるそうです。
ただし、「通勤災害」の条件を満たすには、通勤が合理的な経路での自転車移動である必要があります。仕事と関係のないルートを通り自転車事故に遭うと、補償対象にならない可能性もあるため、注意が必要とのことです。
古藤先生によると、労災保険は被害者にとって多くのメリットがあるため、利用可能な条件を満たす場合は積極的に利用することを検討するといいそうですよ。
自転車事故の過失割合は複雑?交渉が難航したらどうすればいい?
自転車事故の過失割合についても古藤先生に伺いました。
過失割合はお互いの主張を確認し、話し合って決めることになりますが、事故状況の確認をしたり、お互いの主張に違いがあれば交渉する必要があります。相手が保険会社の場合、法律知識や経験の差もありますし、相手が無保険で当事者と直接交渉する場合は、そもそも交渉に応じてもらえない、お互いの主張の折り合いがなかなかつかないなど、自動車事故以上に示談交渉が難航する可能性が高いとのこと。
そのため、過失割合を決める際は、専門家である弁護士に依頼するのが良いそうです。弁護士に依頼することで、「労力のかかる複雑な示談交渉を任せられる」「自分で示談交渉を行わなくて済むので、治療に専念できる」「専門的な判断基準で、納得のいく損害賠償を請求できる」といった多くのメリットがあります。また、弁護士費用特約が利用できる場合は、費用がかからないケースも多いとのことです。
弁護士法人・響でも、自転車事故の相談を受け付けているそうですよ!
自転車同士で交通事故被害に遭った場合も、弁護士法人・響にご相談ください。