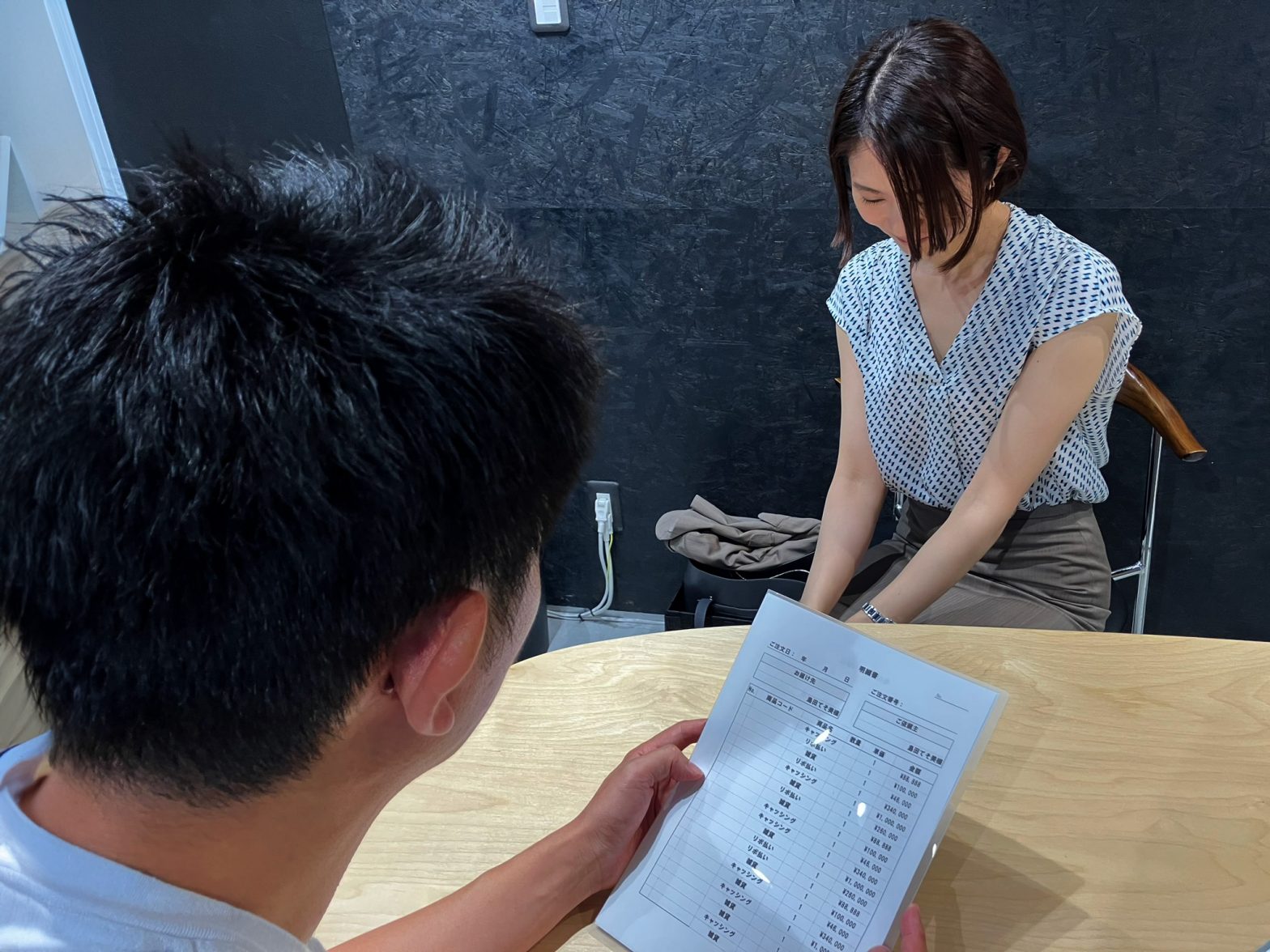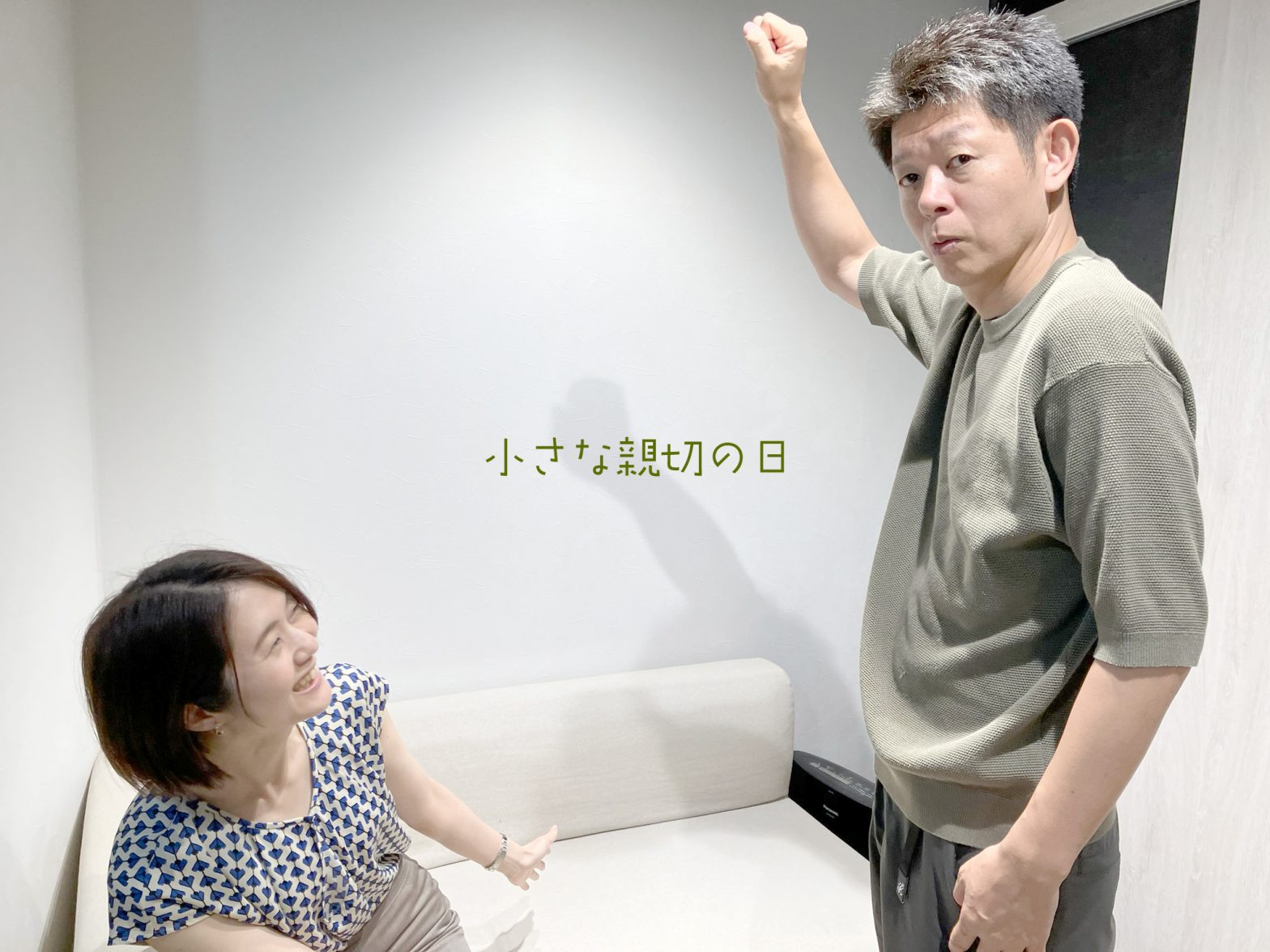10月も終わり11月が来るということで、今年一年の速さについてのお話から始まりました。外出自粛などが続き、イベントや季節の行事なども少なかった今年は、特にあっという間に感じましたね。
さて、第九十一回目は「飲食店の食べ物がメニュー写真と全然違う!これって詐欺?!」をテーマに、坂口先生に詳しく教えていただきました。
飲食店で、出てきた食べ物が実物と違ってがっかりした経験って、誰しもありますよね。
騙されたような気持ちになることもあるかもしれませんが、実際に飲食店を「詐欺」で訴えることはできるのでしょうか?
「詐欺」を立証させるには、この場合“お店側に騙そうという内心がある事”を証明しなければいけません。そのため「詐欺」で訴えることは非常に難しいとのことです。
しかし、このようなケースでは、客観的な判断によりお店側に対して「債務不履行」であると主張できる可能性があります。
お客さんが料理を注文することによって、お客さんとお店との間に契約が成立します。契約に基づいて、お店はお客さんに料理を提供する義務を負い、お客さんは料理の料金を支払う義務を負います。メニューに掲載されている写真より明らかに少ない分量の料理が提供された場合、お店側が注文通りの料理を提供する義務を果たしていないことになるので「債務不履行責任」を負うことになります。
もし、実際に飲食店で写真と異なるものが提供された場合には、「債務不履行責任」に基づいて、
・注文のキャンセル
・代金を払わないこと
を主張することができるそうです。
また、メニューに記載されている分量だから注文した、ということで「錯誤無効」を主張することが可能な場合もあります。
メニューの下に、“※写真はあくまでもイメージです”とある場合でも、写真と同等のものが出てくると期待するのは当然ですので、同じく主張することが可能です。
しかし、出てきたお料理を食べてしまった場合には、不十分な料理の提供であっても“履行を承認した”とみなされ、キャンセルや代金を払わないといった主張は通用しないのでご注意ください。
また、写真と異なるメニューが繰り返し何度も提供されている場合には、不当な広告をしている点が問題になる可能性があります。「不当景品類及び不当表示防止法(景表法)」で、実際のものよりも著しく優良なものであると消費者を誤認させ、不当な表示であると認められた場合には、消費者庁や都道府県が、お店に対して誤認させるような表示をする行為を差し止めたり、再発防止の措置を取るよう命じたりすることができるそうです。
悪質な場合は、課徴金を払うように命じることもあるとのことですよ。
おかしいなと感じた場合には、消費者庁が被害情報を受け付けている窓口がありますので、消費者庁に連絡してみてくださいね。
▼消費者庁 申出・問合せ窓口
https://www.caa.go.jp/policies/application/inquiry/