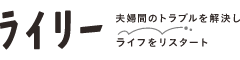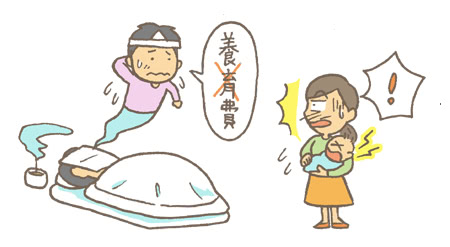浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

遺族年金を受給するための条件
まず、支払い者が加入している年金の種類から見ていきましょう。
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。わかりやすくいえば、遺族基礎年金が国民年金への加入によって発生し、遺族厚生年金が厚生年金(社会保険)への加入によって発生します。
そして、子どもが遺族年金を受給するためには、大まかに下記の条件を満たしていなければなりません。
・養育費の支払い者が国民年金、あるいは厚生年金の被保険者であること
・被保険者の年金制度への加入期間のうち保険料納付済期間と保険料の免除や特例期間を合算した期間が3分の2以上あること(平成27年9月現在)
・子どもが18歳に達してから最初の3月31日を迎えていないこと、または、子どもが20歳未満の子であり、第1級、第2級の障害があること
・子どもが結婚していないこと
遺族年金の支給停止について
遺族年金は、子どもが死亡したり、婚姻したりすると受給権がなくなります。その他にも、子どもが親族以外の者の養子になった場合も同様です。
また、遺族基礎年金は、子どもが両親の一方と生計を共にしていれば、支給されません。
つまり、現実的には遺族基礎年金が支給されることはほとんどなく、遺族厚生年金でなければ受給することはできません。
その他にも、子どもに850万円以上の年収がある場合も受給停止されますが、こちらは稀なケースとなっています。
遺族年金と児童扶養手当は同時に受け取れない
なお、遺族年金と児童扶養手当(詳しくは「離婚後に受給できる公的給付は?」)は、同時に受け取ることができません。
よって、遺族年金を受給したいのであれば、児童扶養手当の受給を解除する必要があります。
金額的に見れば、遺族年金のほうが年間支給額も多くなる傾向がありますが、それも結局は被保険者の収入次第(厚生年金を支払ってきた金額)となりますので、どちらが良いかはケースバイケースとなっています。
いずれにせよ、相手の死亡によって養育費が支払われなくなっても、遺族年金という救済措置が残されていると覚えておきましょう。