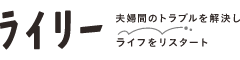浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

産まれてくる子どもの親権は原則として母親に
妊娠中に離婚届を提出する場合、産まれてくる子どもの親権者は原則として母親となります。
しかし、離婚成立が長引き、離婚よりも子どもが産まれてくるのが早かった場合、親権は両方の親が持つことになり、離婚後は親権者の指定、子の氏(姓のこと)や戸籍といった問題が生じます。
後から子の氏を母と同じに変更するには家庭裁判所の審判手続きを経なければなりません。また、戸籍についても母の戸籍への転籍手続きが別途必要となります(詳しくは「離婚すると戸籍はどうなる?」)。
戸籍は300日が基準で取り扱いが異なる
なお、離婚前後の子どもの戸籍の取り扱いは少し複雑となっていて、離婚届が受理されてから300日以内に産まれた子どもであれば、戸籍簿上、子どもには婚姻時の父が記載されます。
上記のとおり、親権者は原則として母親です。
しかし、300日以上経過してから産まれた場合、「非嫡出子(婚姻関係のない男女から産まれた子)」とされ、そのまま母親の戸籍に入ります。
この場合、上記の転籍手続きは必要ありませんが、場合によっては父に対して認知請求しなければなりません。というのも、非嫡出子は戸籍簿上、父の欄が空欄になってしまうため、このままでは父が亡くなった際に相続権も発生しませんし、後述する養育費の問題も出てきてしまいます。
認知を認めるかは相手次第となりますが、子どもの将来のことを考えれば認知してもらうに越したことはありません。
養育費は当然ながら発生するが・・・
では、養育費はどのように取り扱われるのでしょうか?
養育費は、子どもの親である以上、必ず発生するものです。
妊娠中の離婚であっても、親権を持たない方の親に対して養育費は発生します。
しかし、上記のように法律上は非嫡出子とされてしまった場合、父に子どもを認知してもらわなければ法的な扶養義務が発生しないため、注意が必要です。
子どもにとって養育費があるとないとでは成長に著しく影響を与えるため、可能な限り認知してもらいましょう。なお、相手が話し合いで認知に応じない場合、裁判による認知請求も可能となっています。
ただし、認知してもらうにはこの裁判が非常に重要となるため、失敗しないためにも弁護士に相談してから行うのが良いでしょう。