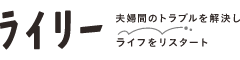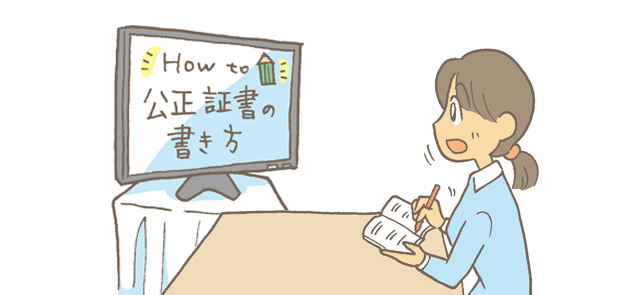浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

目次
養育費が決まったらなぜ公正証書が必要なの?
公正証書とは、協議離婚における「夫婦間の約束事(特に金銭債権)」に執行力を持たせるための書面です。
万が一約束が破られた場合、相手方に履行を求めて裁判上の支払督促・差押えを実行できます。
養育費を払わない親は多い!
厚労省が全国の母子家庭を対象に調査した結果では、養育費について具体的な取り決めしている家庭は全体の約42%・支払われている最中の家庭は全体の約24%という、驚愕のデータが発表されています。
「自分たちは円満に離婚するし、きちんと取り決めも交わすから大丈夫」と思っても、油断はできません。書面で残す場合でも、私文書ではなく公文書として残せる「公正証書」が安心です。
公正証書の仕組みとは
先ほどもお話ししたとおり、養育費は離婚時に取り決めてたとしても、なかなか約束通りに守られないというのが実情です。
公正証書は、国に任じられた「公証人」が作成する公文書であり、高い法的効力があります。
離婚協議の内容を記しておくものとして他に「離婚協議書」などがありますが、私的な契約書にすぎず、未払いになった場合に直ちに強制執行ができません。
しかし協議離婚で合意した内容を公正証書に記載することで、強制執行の機能を備える強力な契約書となります。
いい換えれば、養育費を支払う方からするとリスクが大きい書面でもあります。そのため作成を嫌がられるかもしれませんが、子どもが自立するまで責任を全うしてもらうためにも、きちんと作成しておくことが賢明でしょう。
公正証書の効力やメリットは3つ
離婚時に決める養育費の支払いについて、公正証書を作成するメリットは以下の3つです。
1. 養育費の支払いが滞っているときに有効
養育費支払いの約束を守ってもらえない場合は、裁判上の証拠書類として利用することができます。法的な回収手段として「養育費調停」または「民事裁判(通常の債権回収手続き)」が挙げられますが、いずれの場合でも支払い義務の存在を認めて迅速に判決をもらうための足掛かりとなります。
2. 自由に決められるからこそ法的拘束力が欠かせない
養育費の金額・支払い期間などの詳しい条件は、法律で定められているわけではありません。原則として、夫婦間が自由に決定してもよいとされています。これを良いことに、後で勝手に金額を減らされる・約束を反故されるといったケースが後を絶ちません。
公正証書では「支払日」「金額」「支払期間」を含む詳細な取り決めについて、それぞれ文書上で法的効力を持たせることができます。あとから相手方の都合に振り回されることなく、合意した養育費の条件をしっかり履行してもらえます。
3. 養育費は“約束した証拠”さえあれば手厚く保護される
養育費は、他の金銭債権よりも手厚く保護されています。具体的な保護内容をまとめると、次のとおりです。
【養育費回収に認められている保護内容】
差押禁止債権※が3/4から1/2まで圧縮される(民事執行法151条2項・152条3項)強制執行の際、養育費とは別の「間接強制金」を裁判所に課してもらうことができる(民事執行法167の条15第1項)
※差押禁止債権とは
給料・退職金・年金など、差押えをすることで債務者の生活が維持できなくなるために、差押えを禁止された債権のこと
差押申立をしても、本来なら相手方の給料の1/4までしか回収することができません。しかし養育費未払いトラブルであれば、1/2まで回収できる金額が広がります。また、養育費とは別の“罰金”を裁判所から提示してもらうことで、相手方に心理的なプレッシャーを与えることができます。
以上が公正証書を作成するメリットです。
重要なのは、子どもが安心して過ごせる生活を用意すること。一人で子どもを育てるには大きな苦労を伴います。せめてお金の心配だけでも少なくしておきたいものですよね。
公正証書は養育費の未払いを防ぐだけでなく、安心した生活を保証してくれるお守りにもなってくれるでしょう。
養育費の支払いにおける公正証書の作り方
公正証書作りで最も大切なのは「何について・どのように内容として盛り込むべきか」という点です。離婚協議では養育費はもちろん、財産分与・慰謝料などお金にまつわる取り決めが多く発生します。
お金の問題はただでさえトラブルになりがちなものです。その上、公正証書は公的文書ですから、記載内容に漏れ・あいまいな部分があっては、約束そのものが無効になる可能性もあります。
子どもの権利を守るためにも、確実に作成することが大切なのです。
続いて、公正証書の作り方についてじっくりお話ししていきますね。
公正証書作成の流れ(3ステップ)
公正証書の内容を決め、協議書あるいは公正証書原案など書面化したものを持ち込んで夫婦共同(あるいは弁護士など代理人でも可)で手続きを行います。所要時間は30~1時間程度・証書完成までの日数は10日程度です。
1.離婚協議書または公正証書原案を作成する
まずは夫婦で決めた内容を「離婚協議書」または「公正証書原案」として記録しましょう。離婚や養育費について公正証書を作成するときに、決めるべき必要事項は以下のとおりです。
【参考】離婚協議書(または公正証書原案)に盛り込むべき条項
- 離婚の合意
- 親権者と監護権者
- 子供との面会交流と養育費
- 離婚慰謝料
- 離婚による財産分与
- 住所変更の通知義務
- 清算条項※
- 強制執行認諾 ※後ほど詳しくお話しします
※清算条項とは?
当事者間に、公正証書に記載した権利・義務関係のほかには、何らの債権債務がない旨を当事者双方が確認する条項のことです。
2.夫婦で公証役場に行き、公証人と面会する
公証役場へ向かう日時は事前に予約可能です。
日本公証人連合会で夫婦双方の居住地から近い場所を探しましょう。営業時間は他の官公庁と同じく平日9~17時であるため、夫婦それぞれが仕事・家庭の予定を調整して予定を組む必要があります。なお、夫婦同席が難しいような状態であれば、弁護士など代理人を立てることも可能です。
【公証役場での手続き内容】
- 作成した書類+他の必要書類等(詳細は後述)を提出
- 公証人に協議書内容を確認してもらい、必要な条項についてアドバイスをもらう
- 受け取り時の流れや作成後の注意点などについて案内してもらう
※弁護士作成の「離婚給付契約公正証書(原案)」があれば3のステップはなく、その場で公正証書の作成が完了します。
3.後日再び夫婦で公証役場に行き、原案をチェックして手続き終了
離婚協議書を提出した場合、公証人が作成した公正証書原案をチェックするために再度来庁が必要です。
公正証書原案の内容に夫婦が合意すると、謄本(正本の写し)が計2通発行されて手続き終了です。
公正証書を作成費用・準備するものは?
当日の持ち物のうち、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)以外にも印鑑証明書・戸籍謄本が必要である点に注意してください。
【公正証書作成に必要なもの】
- 離婚協議書または離婚給付契約公正証書(原案)
- 所定の手数料(後述)
- 夫婦両名分の戸籍謄本・実印
- (同上)印鑑証明書
- (同上)本人確認書類
- (年金分割を行う場合)夫婦双方の年金手帳・情報通知書
- (分与する財産に不動産がある場合)登記簿謄本・物件目録
公正証書の作成費用(手数料)
公正証書の作成に必要な手数料は、養育費+慰謝料の合計額に応じて異なります。協議書または原案作成が完了したら、忘れず手数料を確認しましょう。不明の場合、弁護士に質問して調べてもらうのが確実です。
| 公正証書の目的価額※の金額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超~200万円 | 7,000円 |
| 200万円超~500万円 | 11,000円 |
| 500万円超~1,000万円 | 17,000円 |
| 1,000万円超~3,000万円 | 23,000円 |
| 3,000万円超~5,000万円 | 29,000円 |
※公正証書の手数料(参考:日本公証人連合会)
※目的価額=養育費+慰謝料
養育費は「強制執行認諾条項付き」がおすすめ!その理由は?
金銭に関する約束事が盛り込まれた公正証書には、任意で「強制執行認諾条項(以下、執行認諾)」が付与可能です。
夫婦で自由に決めてもいいものですが、より確実な安心を得るために執行認諾付与をおすすめします。
なぜなら執行認諾がある公正証書の法的効力は強まり、裁判なしで強制執行による差し押さえを行うことができるからです。
【参考】裁判による養育費回収手続き
- 相手方に内容証明送付
- 民事訴訟の申立(公正証書などを証拠資料として提出)
- 判決・債務名義※の獲得
- 仮執行申立
- 債券名義に執行文付与
- 強制執行の申立
※債務名義とは:
強制執行によって実現される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公文書です。これに執行を許可する文書(執行文)を付与してもらうまで、債権回収の最終フェーズに入ることはできません。
執行認諾付きの公正証書は、3で得られる債務名義と同じ役割を果たします。したがって2~3の手続きを省略し、仮執行申立から養育費回収を始められるのです。
執行認諾付き公正証書に認められる新しい権利(2020年4月施行)
執行認諾付き公正証書があれば、裁判所の許可を待たずに相手の財産を差し押さえることが可能です。
そのためには「相手のどの財産を差し押さえるのか」を裁判所に申し立てなければなりません。したがってあらかじめ相手の財産を把握しておくことが重要になります。
しかし2019年現在、養育費を回収する際、相手方のその時点での預金口座・勤務先を知らないと、たとえ公正証書があったとしても差し押さえは困難です。
「財産開示命令」を出し、相手方が財産目録を提出する。命令に強制力はなく、官公庁や年金機構で相手の情報を調べることも許されていません。
2020年4月からの民事執行法改正では、財産開示命令の要件に,今まで除外されていた執行認諾文言付き公正証書が加わり,第三者からの情報取得手続きが創設されました。
認められる権限が今後広がることを念頭におくと、執行認諾の条項は一人で子どもを育てる親の“お守り”としてますます欠かせない要素となりうるものです。
離婚後に“もしも”が起こった時の公正証書の使い方
公正証書を作成した後でも、増額や減額はできるのでしょうか?
結論からいうと、公正証書を作成した後からでも、増額や減額は可能です。
理由はさまざまですが、大きく増額・減額認められるケースについて3つのポイントをご紹介していきます。
増額が認められるケース
- 急激な経済状況の悪化
- 養育をおこなっている親や近親の人の失業や疾病による増額
- 私立など費用の掛かる学校への進学による増額
減額が認められるケース
- 支払う側が疾病や事故により収入がなくなる
- 支払う側が解雇などの理由により失業してしまう
- 子どもを引き取っている側が再婚し、養子になった場合
支払う側の経済状況、子ども自身の進路の費用など増額するにも減額するにもさまざまな理由があることがわかりました。これらの最終的な決定については父母の協議によって決まります。
強制執行の手続きはどうすればいい?
公正証書を作ったとしても、養育費を支払わないケースはありえます。
未払いについて相手から誠実な回答がなければ、やはり強制執行による差し押さえに踏み切らざるをえないでしょう。
では、強制執行の手続きについてみていきましょう。
強制執行は以下のような流れで行われます。
- 公正証書を公証役場に持っていく
- 債権差押命令申立書を作成する
- 裁判所に申し立てをする
- 差し押さえ命令
- 養育費の取り立て
なお、強制執行を行うためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
1. 相手の現住所や財産を把握していること
強制執行できる財産は、不動産や債権、預金口座などの種類があります。
養育費を差し押さえするには、相手がどれだけ財産を持っているかを把握しなければなりません。
差し押さえとなる対象を裁判所で説明しなければならないため、相手の現住所、勤務先、預金口座を把握しておく必要があります。これらの情報を獲得するのが困難であれば、弁護士や探偵に依頼してもらうことをおすすめします。
※2020年4月からの民事執行法改正では、執行認諾付き公正証書がある場合に限り「裁判所の許可なしで財産開示命令を出せる」というルールに変更されます。
2. 債務名義を持っていること
ここでいう債務名義とは、養育費を請求する権利を証明した書面のことを指します。
債務名義として以下のような書類が挙げられます。
- 和解調書
- 調停調書
- 確定判決
- 公正証書
公正証書もこの債務名義にあたりますので、強制執行をするにあたり、有効な書面として証明できます。
上記の条件を満たしていれば、債権差押命令申立書を作成でき、相手の財産を差し押さえることが可能です。
未払い養育費の差し押さえについては、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。