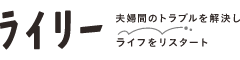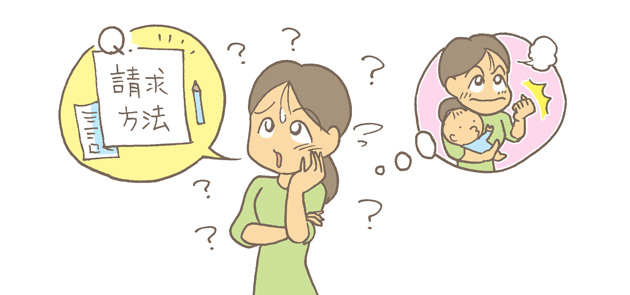浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

目次
養育費は離婚後でも請求することが可能
そもそも養育費とは?
養育費は子供が社会人になり、自力で生活できようになるまでの間に必要な費用です。
夫婦は婚姻関係があれば別居していても、子どもの生活費や養育費を分担しなければなりません。
たとえ「離婚後は別居していて子どもと会っていない」状態でも養育費の支払い義務は変わらないのです。
これは民法でも明確に定められています。
同様に民法では、子どもとの面会や交流、養育費の分担などの取り決めについては、話し合いによる決定が尊重される、としています。
つまり「養育費の支払いは義務ですが、話し合い次第ではどうにでもなる」が本当のところなのです。
養育費は変更できる
離婚協議での決定内容については、あとになって変更するのも可能です。
たとえ決定事項を公正証書のような法的効力のある書面にしていても、再度協議すれば、新しい内容に書き換えることもできます。
特に養育費は、長期間支払い続けるものです。その間、生活にどんな変化が生じるかはわかりません。
「子どもが重大な病気になった」「会社の業績が悪化して給料が減った」など。離婚時に養育費は不要と決めていても、あとになって必要になるケースは十分にありえます。
「一度決定したものは変えられない」と思われがちなのですが、数年してから必要になったとしても、請求や増額(や減額)も可能ですので安心してください。
未払い養育費の請求も可能
「せっかく離婚時に養育費について決めたのに、相手が支払ってくれない」
残念ですが、このようなケースは意外と多いです。
もちろん離婚時に取り決めた養育費が支払われない場合も、相手方に請求できます。
養育費を含めて離婚協議の決定は、いわば契約であり、その後は遵守しなければなりません。
契約どおりに支払われない場合は連絡して話し合い、または内容証明郵便で未払い分の請求となります。
ただし未払い期間が長いと請求額も高くなりますので、相手方もそう簡単に応じられないケースも多いです。したがって話し合いでの解決は、現実に難しいです。
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所による調停・審判に委ねられます。
「相手方が養育費を払わないときの対処法」について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
養育費を請求するため金額・期間などの条件
ここまで養育費の支払いは親の義務であり、離婚してから数年を経った場合でも養育費の請求は可能とお話ししてきました。
とはいえ、いくらでも、いつまででも請求できるわけではありません。
金額や期間については一定の目安やきまりが定められています。
ここからは、相手との話し合いで請求を妥当なものにするためにも、ぜひ知っておきたい養育費の金額や期間についてお話ししていきましょう。
養育費はいくら請求できるのか?
では養育費はいくらであれば請求できるのでしょう?
基本的には当事者同士での話し合いで決まりますが、お金のこととなると、お互い譲れない場面も発生するかもしれませんね。
養育費の金額については、東京と大阪の裁判所が公表した「養育費算定表」をもとに決める、というのが一般的になっています。
養育費算定表は子どもの年齢、子供の数、夫婦の年収に応じて支払われるべき金額が定められ、仮に裁判になった場合でも参考にされるものです。
とはいえ養育費の金額は、最終的には当事者の合意が重要です。単なる目安と考えておきましょう。
また話し合いがうまく進まず、養育費の金額に納得ができないという場合は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士は法律のプロだけでなく、法律の知識を駆使した交渉のスペシャリストでもあります。
より希望している金額に近づけるためにも、弁護士の交渉力を活用してはいかがでしょうか。
養育費はいつまで受け取れるか?
養育費というと成人するまでのイメージがありますが、具体的にいつまで請求できるのか気になりませんか?
一般的に子どもが自立する18~22歳まで請求することが可能です。
法律用語で扶養義務がある子どものことを「未成熟子」と呼びます。
これは未成年を指すのではなく、在学中であったり、病気・身体障害で働けなかったりといった理由で経済的な自立ができない子供を指します。
たとえば子どもが大学に進学し、ストレートで卒業したとした場合は年齢が22歳まで請求できます。
離婚時の取り決めで18歳までとしていても、大学への進学が決まれば卒業まで期間を延長することが可能です。
ただし期間を延長する場合も相手の合意が必要なため、再度話し合わなければいけません。
養育費は子どもが請求することも可能
あまり知られていませんが、養育費は子ども自身が請求することも可能です。
そもそも、養育費を受け取る権利は親ではなく子どもにあります。したがって子ども自身の請求は正当な要求といえますよね。
とはいえ、離婚協議の段階で親に対して子どもが養育費を請求ケースはほぼないといっていいでしょう。
大学へ進学や留学などさまざまな事情から、最初に取り決めていた養育費では足りない場合、子どもは親に対して養育費とは別に「扶養料」として請求可能です。
扶養料は親に対して直接請求できる権利です。未成年の場合は親権を持つ人が代理人として請求しますが、一般的に扶養料よりも養育費の請求を行うことが多いです。
そのため、扶養料は成人に近い子どもが用いるケースが一般的で、大学へ進学するときなどで利用されています。
養育費が請求できないケースもある
一方で離婚後に養育費を請求できないケースも存在します。
養育費を請求できない場合
1.原則、請求した以降の養育費のみ
養育費の支払いは原則として、養育費請求を行った以降の分だけが認められます。
たとえば、離婚時には養育費の取り決めをしておらず半年後に請求した場合、請求する前の半年分の養育費については請求できません。
2.養育費にも時効がある
離婚時に養育費の支払いについて、元夫婦間で合意があった場合も注意が必要です。
未払いの養育費については、養育費を請求する権利も行使しないと、時効によって認められないケースがあります。
ただし未払い開始から時効までの期間はケースバイケースですが、まとめると以下のようになります。
| ケース | 時効 |
|---|---|
| 協議離婚時に養育費の取り決めがなされ、公正証書を作成した | 5年 |
| 協議ではなく家庭裁判所の調停や審判で養育費を決定した | 10年 |
| 養育費を決めずに離婚した、養育費を決めたが口約束で書面にしていない | なし |
もし養育費の時効期間を過ぎてしまうと、未払い分の養育費と、将来分の養育費を支払ってもらえなくなります。
時効があることだけを考えると「養育費の取り決めはしない方がいいのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、公正証書などの“証拠”がないと、未払い分の請求調停や裁判を起こした場合に、不利益が生じる可能性があります。
子どものためにも養育費の不払いは泣き寝入りできないもの。不払いが発覚した段階で早めに請求しましょう。
養育費を請求する方法と流れ
実際に養育費はどのような流れで請求するのでしょうか?
離婚協議時であっても、離婚してしばらく経ってからでも流れは同じで、大きくは以下の3ステップとなっています。
- 協議
まずは元夫婦で話し合い、養育費の支払いの取り決めをしていきます。 - 調停
協議で請求が認められない場合は、相手方住所の家庭裁判所に養育費請求の調停を申立てましょう。 - 審判
養育費請求調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始されます。審判は、裁判官が一切の事情を考慮して判断します。
それでは、それぞれの流れをもう少し詳しくご紹介しましょう。
元夫婦間での協議
まずは相手方に連絡を取り、話し合いで養育費の支払いを決めていきます。
具体的に決める内容は次の3点です。
- 養育費の金額
元夫婦の現状の収入や子供の数・年齢などを考慮して総合的に決めます。
金額を決めるまでの基準となるのが、養育費算定表です。
養育費算定表は東京や大阪の裁判所が策定したもので、実際の調停や裁判でも基準として採用されています。 - 養育費の支払い方法
一般的には毎月定額で振り込んでもらうケースが多いです。
年払いや総額の一括払いも可能です。 - 養育費を支払う期限
子どもが何歳になるまで支払うのかなどの、期限を設定しましょう。
養育費の取り決めは話し合いで解決できるのがベストです。
とはいうものの「もう相手と話したくない」「親権を奪われたらどうしよう」という気持ちもあるかもしれませんね。
忘れてはならないのは、養育費は子どもに支払われるためのもの、ということ。 親権が父母どちらであっても子どもに対する扶養義務は変わりません。「親権がないから養育費は支払わなくていい」は成立しないのです。
冷静になって、子どもの将来や生活のために話し合う、というスタンスで望むことが大切です。
公正証書の作成・費用は?
未払いの対策として金額や毎月の支払い日、期間などが決まったら、必ず公正証書に残しておきましょう。公証役場に足を運んで公証人の立会いの元、作成します。
作成には次の手数料が発生します。
| 養育費や慰謝料等の合計金額 | 公証人手数料 |
|---|---|
| ~100万円 | 5,000円 |
| ~200万円 | 7,000円 |
| ~500万円 | 11,000円 |
| ~1,000万円 | 17,000円 |
| ~3,000万円 | 23,000円 |
| ~5,000万円 | 29,000円 |
公証役場によっては別途で用紙代などの雑費がかかる場合があります。
実際に作成する場合は窓口で確認してみてくださいね。
養育費請求調停
協議で請求が認められない場合は、相手方住所の家庭裁判所に養育費請求の調停を申立てましょう。
- 養育費請求調停とは?
調停とは、裁判所が当事者同士の間に入り、話し合いで適正な解決に導いてくれる制度です。
養育費請求調停は、相手方の住所が管轄する家庭裁判所に申立てることで、養育費の支払いや金額の変更を請求できます。
この調停でも話がまとまらない場合は、自動的に審判に移ります。
なお、未払いの請求をする場合、公正証書の有無に関わらず、協議なしでも調停を申し立てることは可能です。
また、公正証書がある場合は、調停を申し立てず強制執行に進むのが一般的な流れとなっています。
【調停にかかる費用】
養育費請求調停では、収入印紙と郵便切手の費用が発生します。
- 収入印紙
子ども1人あたり1200円分(子どもの数だけ申立てが必要) - 郵便切手
家庭裁判所によって異なる
【調停に必要な資料】
調停に申立てる際は、主に3つの書類が必要です。
-
- 調停申立書
インターネットなどで取得可能です。
- 調停申立書
-
- 収入を証明する書類
・給与明細書
・源泉徴収
・無職の場合は非課税証明書
・生活保護受給者は生活保護受給証明証
これらの書類が収入の確認書類に該当するので、いずれかを用意してくださいね。 - 子どもの戸籍謄本
本籍地の役所から戸籍謄本を取り寄せてください。
取得する際、1通あたり450円の費用が発生します。
- 収入を証明する書類
家庭の事情によっては他にも必要となる書類が発生する可能性があります。
調停では、調停委員が双方から収入の状況や子どもの状況などを聞き、最適な養育費の金額を提示します。
ここで合意がなされなければ最終的に裁判官による審判へと移ります。
調停は裁判所で行われるもので、必要書類も複雑ですし、調停委員とのやりとりも発生します。調停はあくまで双方の合意がゴールですが、調停委員の心証も大事になります。
調停にかかる手間や負担を減らすだけでなく、確実に進めるためにも法律のプロである弁護士に相談してみましょう。
養育費請求審判
調停でも合意に至らない場合は、自動的に審判へと移行します。
- 養育費請求審判とは?
- 調停での話し合いを踏まえた上で、裁判官が養育費の支払いや金額などを判断する制度です。裁判所による判断ですので、当事者の合意は必要ありません。
審判が行われると「審判書」と呼ばれる審判内容を記載した書類が作成されます。
もし養育費を支払う側が決まりを守らず未払いが続く場合、審判書を債務名義にして強制執行が可能です。
強制執行とは相手方の給与や預貯金などの資産を差し押さえ、養育費を強制的に回収する制度です。
審判の大きなメリットは強制力の高さといえるでしょう。一方で、自身の主張に確実な根拠や証拠が裁判官に伝わらなければ、不利な結果に終わる可能性もあります。
審判でも費用がかかりますが、金額は調停とほとんど同じです。
審判にかかる費用
- 収入印紙
子ども1人あたり1200円分(子どもの数だけ申立てが必要) - 郵便切手
家庭裁判所によって異なる
養育費の請求は話し合いが難航することも…
離婚してからしばらく経ってからでも、養育費は請求できます。
相手に養育費を請求してすんなり支払ってくれるのであればいいのですが、やはりお金が絡むとお互いそう簡単に合意が得られない可能性があります。
それだけでなく「今さら相手と話したくない」という気持ちもあるかも知れませんし、
相手も同じような感情を抱くかもしれません。
こうした背景から養育費請求の話し合いは難航する可能性があります。
当事者の話し合いで合意がなされない場合は、裁判所での調停や審判に移行します。
調停にせよ審判にせよ、複雑な書類を作成し、調停委員や裁判官からの質問に応じなければなりませんので当然、心身への負担も大きくなります。
話し合いがこじれて長期化しないためにも、弁護士への相談がおすすめです。
最後に弁護士に依頼するメリットとデメリットを確認しましょう。
養育費請求を弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼することで、主に次のメリットがあります。
- 調停委員とのやりとりのフォロー
法的な知識を活かし、調停を有利に進めて早期解決を見込めます。
調停委員からの解決策に対して、妥協すべきところを見極めることが可能です。 - 申し立ての手続きや書類作成の一任
手間がかかる調停申立ての手続きや書類作成をお任せできます。 - 精神的な負担が軽減される
調停後、元配偶者との連絡は弁護士を通じて行うので、直接連絡する必要はなく、精神的な負担を軽減できます。
仕事などで調停に出られない時も、代理出席してもらえるので安心です。
もちろん、養育費の請求は当事者の話し合いによって解決すべきです。
しかしどうしても解決できない場合は、弁護士に相談してみましょう。