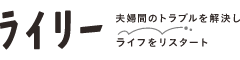浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

目次
養育費は贈与税や所得税など課税の対象になる?
まず、養育費には贈与税や所得税などの税金はかかるのでしょうか?
原則、養育費に所得税や贈与税など税金はかかりません。
そもそも養育費は離婚に伴い、一方の親権者から子どもの生活費や医療費などの分担金として支払われるものです。
法律上では扶養義務に基づき支払われるものであり、あくまでも子どもが健やかに成長できるようにするものなので、原則的に非課税となっています。
相続税法21の3第1項2号によれば、このように記載されています。
- 相続税法21の3第1項2号
- 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの。
課税された後の生活費を被保険者の生活費に配分する養育費は、目的通りの給付ができていれば課税する必要がないと判断されます。
わかりやすくいうと、養育費は支払っている親は、給与を受け取る時点ですでに所得税を支払っています。そのため、給与の一部を別居している子どもの生活費や学費に充てても課税対象にはならない、というわけです。
毎月、養育費をもらっている側の親にとっては「収入」と思いがちですが、養育費はあくまで支払っている側の親から子どもに渡しているお金。したがって収入に応じて支払う所得税の対象とはなりません。
しかし、贈与税に関しては例外があります。
その例外とは養育費を一括払いにしているケースです。
養育費を一括で支払うと相当な金額になる場合があります。そうすると「支払う時点で子どもの生活に必要な限度を超える」とみなされて、贈与税の課税を受ける可能性のあるのです。
たとえば、毎月5万円の養育費を支払う必要があるとしましょう。
その養育費を10年分まとめて支払うと、合計600万円になります。
600万円の養育費を一括払いすると、贈与税は約82万円かかる計算となります。
計算式
600万円-110万円(基礎控除分)=490万円
490万円×30%(控除後の税率)=82万円
毎月の支払いであれば、贈与税はかからないことを考えると、養育費の一括払いはデメリットが大きいといえるでしょう。
養育費を払っていると扶養控除が受けられる?
「養育費を払っているのだから、扶養控除は適用されるのでは?」
夫婦であれば、子どもの扶養控除は、収入の多い側の親を対象にするのが一般的でしょう。では離婚したらどうなるのでしょうか?
実は養育費を支払っていると、扶養控除を受けられる可能性があります。
ただし、扶養控除を受けるためには条件があります。
以下でその内容を詳しくご紹介しましょう。
そもそも扶養控除とは?
最初に扶養控除について、少しお話ししておきますね。
扶養控除は、納税者に所得税法上の「控除対象扶養親族」がいる場合、一定の控除が受けられる制度です。
ここでいう控除対象扶養親族は、扶養親族の中でもその年の12月31日時点で16歳以上の子どもを指します。
扶養親族に該当するには、国税庁のHPによると以下の条件を満たす必要があります。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること<br(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
養育費を支払っている側の親の立場だと、(2)の「納税者と生計を一にしている」とはいえないとお思いかもしれません。
しかし、子どもの生活費や学費、医療費などを用立てているという点では「生計を一としている」と見なされ、扶養控除が受けられる可能性があります。
もちろん、離婚してから養育費の支払いを継続していることが最低限の条件になります。
ちなみに、仕送りなどで自分の親に送金をしている場合は、親も控除対象の扶養親族と見なされます。
扶養控除を受ける際の注意点
実際に扶養控除を受ける際には、注意点が2つあります。
1.16歳未満の子どもは控除の対象にならない
まず注意したい点は、「年少扶養控除廃止」についてです。
年少扶養控除廃止というのは、子どもが16歳未満の場合、扶養控除が適用にならないというもの。
かつては、0歳以上16歳未満の子どもについても、年少扶養控除として扶養控除が受けられるようになっていました。
しかし、2011年~2012年の改正で除外されてしまったのです。
現在は、子どもを対象にした子ども手当が支払われていますが、子ども手当の財源確保が廃止につながったと考えられています。
そのため、子どもが16歳未満の場合は、たとえ養育費を支払っていたとしても扶養控除を受けることができないのです。
2.一方の親のみ適用
また扶養控除は一方の親しか適用されない点も要注意です。
扶養控除は、基本的に申請をした者が控除の対象になります。
親権に関係なく所得税が多い方になる可能性が高いですが、やはり理解してもらう努力が必要不可欠です。
話し合いをする際には、扶養控除の権利をもらう代わりとして、養育費を多めに支払うといった譲歩も大切です。
お互いに納得のいく形で落ち着けるよう進めていきましょう。
しかし、それでも扶養控除に関しての話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談する方法もあります。
控除できるのはどれくらいの金額
扶養控除を受けられたとして、具体的にどれくらいの金額が控除されるのでしょうか?
扶養控除は「16歳以上19歳未満」と「19歳以上23歳未満」で金額が異なります。
所得税と住民税で見た場合、控除金額は下記の通りです。
| 年齢 | 【16歳以上19歳未満】 | 【19歳以上23歳未満】 |
|---|---|---|
| 所得税 | 38万円 | 63万円 |
| 住民税 | 33万円 | 45万円 |
19歳以上23歳未満で所得がない子どもというと、主に大学生です。
「特定扶養親族」と呼ばれ、学費や家庭に関わる経済的負担が大きいことから、控除額が多めになっています。
年齢によって金額は変わりますが、控除される金額は法律で定められているので、子どもの年齢で確認してみましょう。
扶養控除の手続き方法
では、養育費の扶養控除を受けるために必要な手続きについて紹介しましょう。
(1)養控除申告書を提出
まず、会社員をはじめとする給与所得者は「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を会社に提出しなければなりません。
申告書は、その年の最初に給与の支払いを受ける前日までに提出する必要があります。
添付する書類は以下のとおりです。
養控除申告書で提出する書類一覧
- 勤労学生の証明書
勤労学生控除を受ける場合、それを証明できる書類が1部必要になります。 - 親族関係書類
親族関係書類も1部用意しましょう。
源泉徴収において非居住者である親族に関わる扶養控除の際だけでなく、障害者控除や厳選控除や衣装配偶者の適用を受ける際に必要です。 - 送金関係書類
非居住者の親族に関わる扶養控除を受ける場合、その親族の送金関係書類も用意しなければなりません。
(2)年齢16歳未満の扶養親族申告を行う
先に述べたように、0歳以上16歳未満の子どもは扶養親族における扶養控除は廃止されました。
しかし、非課税限度額の算定の際に使用しなければならないため、必ず申告しなければなりません。
会社勤務ではなく、自営業の場合は申告書を記入したり、特別な手続きをしたりは不要です。
確定申告書を提出する際に、扶養控除に関する旨を記載しましょう。
もし控除を受けられない場合は養育費の変更を検討しよう
最後に扶養控除も適用されず、養育費の支払いが困難になった場合の対処法についてお話します。
養育費の支払いが困難になったら、養育費の減額を請求する方法があります。
養育費は長期間にわたって支払われるものです。その間に子どもの進学や親の勤務先の倒産・失業、再婚など、経済的な事情が大きく変化した場合、養育費の変更は認められています。
養育費を減額する方法についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。
ただし減額できる正当な権利があるからといって、すぐに家庭裁判所に調停を申し立てるのは早計です。子どもの生活にもかかわる問題なので、相手の状況も尊重しながら進めましょう。 そして、どうしても話し合いで解決できない場合は、弁護士や専門家に相談しましょう。