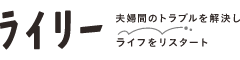浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

目次
ひとり親家庭支援の主な内容
ひとり親家庭の支援制度には、主に次のようなものがあります。
<ひとり親家庭を対象とした支援制度>
- 児童扶養手当
- 医療費助成
- 賃貸住宅の家賃補助
- 所得税や住民税の控除
- 水道料金の減額または免除
- JR定期券の割引
- J粗大ごみ処理手数料の減額または免除
<収入が低い方を対象とした支援制度>
- 国民健康保険料の軽減・減免
- 国民年金保険料の免除や猶予
<働くための支援制度>
- 自立支援教育訓練給付金
- 高等技能訓練促進費
- マザーズハローワーク
児童扶養手当以外は、基本的に自治体によって内容が異なります。それぞれの内容を見てみましょう。
ひとり親家庭を対象とした支援制度
まずは、ひとり親家庭を対象とした支援制度を紹介します。
1. 児童扶養手当
児童扶養手当とは、父母の離婚や死亡などにより、父母どちらか一方からしか養育を受けられない子どものために、養育者に対して支給される手当です。
児童扶養手当は国の制度ですが、各自治体が支給を行います。支給期間は原則として、「子どもが18歳になった年度末」までです。
手当の月額は、子どもの数や養育者の所得に応じて変わります。たとえば全額支給の場合、金額は次の通りです。
- 子ども1人・・・月額43,160円
- 子ども2人・・・月額53,350円
- 子ども3人・・・1人増えるごとに月額6,100円~3,060円を加算
※ 2021年3月現在。支給額は改定されることがあります。
児童扶養手当について、知っておきたいポイントを3つお伝えします。
(1)養育費は所得の扱いになる
「養育費」はその額の80%(1円未満は四捨五入)が所得として扱われます。そして、児童扶養手当の支給額は、所得によって変わります。養育費が高額な場合は、児童扶養手当の額は少なくなる可能性があります。
(2)支給は毎月ではない
児童扶養手当の支給は、毎月ではありません。まとめて支給される制度になっています。
離婚したからといって、児童扶養手当が自動的に振り込まれるわけではありません。手続きした翌月分から発生しますので、なるべく早く手続きすることをおすすめします。
なお東京都には、「児童育成手当」もあります。一定の条件を満たせば、子ども一人につき月額13,500円が支給されます。
詳しくは自治体の窓口やホームページなどで確認しましょう。
(3)児童手当と同時受給が可能
児童扶養手当と名前の似た制度に、児童手当があります。名称は似ていますが別物です。
児童手当は一定の条件を満たせば、「子どもが12歳になった年度末」まで受けられる手当です。児童扶養手当と児童手当は、条件を満たせば両方受け取ることが可能です。
2. 医療費助成
ひとり親家庭の方が病気やケガで医療を受けた場合、一定の条件を満たすことで、自己負担額を軽減する医療費助成が受けられます。
助成の対象期間は、原則として「子どもが18歳になった年度末」までです。
助成の内容や条件などは、自治体によって異なります。たとえば東京都の場合は次の通りです。
<1か月あたりの自己負担上限額>
住民税課税者
- 通院・・・負担なし
- 入院・・・負担なし
住民税非課税者
- 通院・・・18,000円
- 入院・・・57,600円
※ 平成30年3月現在。内容は改定されることがあります。
(参考)東京都福祉保健局:「ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)」
なお医療費助成を受けるには、所定の手続きが必要です。自治体の窓口で手続きを行うと、助成を受けるための「ひとり親家庭等医療費受給者証」が交付されます。
医療機関を受診する際は、健康保険証と共に提示するようにしましょう。
なお医療費の中には、助成の対象外となるものもあります。
たとえば予防接種や健康診断にかかった費用、入院中の食事代や差額ベッド代など、健康保険が適用されない医療費に関しては対象外です。
詳しい内容については、各自治体の窓口やホームページなどでご確認ください。
3.賃貸住宅の家賃補助
ひとり親家庭の支援制度として、賃貸住宅の家賃補助を行う自治体もあります。基本的に所得制限や条件があり、支給額も異なります。
支給される月額はおおむね「3千円~1万円」が相場です。
家賃補助制度を利用するには、所定の手続きが必要です。まずはお住いの自治体が家賃補助制度を実施しているかどうかを調べた上で、必要に応じて手続きを行いましょう。
また、京都市のように、公営住宅に優先的に入居できる制度を実施している自治体もあります。詳しくは自治体の窓口やホームページなどをご覧ください。
(参考)京都市情報館:「ひとり親家庭の市営住宅優先入居」
4. 所得税や住民税の控除
所得500万円以下など一定の条件を満たすと、「寡婦(夫)」として所得控除を受けることができます。
さらに「生計を同一にする子どもがいる」などの条件を満たすと、「特別の寡婦」となり、同じく控除を受けることができます。
寡婦(夫)控除と特別寡婦控除、それぞれの控除額は次の通りです。
- 一般の寡婦・・・27万円
- 特別の寡婦・・・35万円
控除を受けることで、所得税や住民税が軽減されます。詳しい内容については、国税庁のホームページに書かれていますので、チェックしてください。
(参考)国税庁:「寡婦控除」
5. 水道料金の減額または免除
児童扶養手当を受給しているひとり親家庭は、水道料金や下水道料金が減額または免除されることがあります。
たとえば東京都の場合は、次の通り水道料金が減免されます。
- 水道料金・・・基本料金+従量料金(1か月当たり10m³まで)<
- 1か月当たり8m³までの料金
(参考)東京都水道局:「水道料金・下水道料金の減免のご案内」
水道料金の減免を受けるには、申請が必要です。まずはお住いの自治体に制度があるかどうかを確認した上で、所定の手続きを行いましょう。
6. JR定期券の割引
児童扶養手当の支給を受けている世帯のひとり親家庭の方は、所定の手続きをすることで、定期券を3割引で購入することができます。
購入に際しては、自治体が発行する「特定者資格証明書」「特定者用定期乗車券購入証明書」が必要です。
自治体の窓口であらかじめ交付を受け、駅に備え付けてある「定期乗車券購入申込書」と共に提出してください。なお、学割など他の割引制度との併用はできません。
(参考)JRおでかけネット:「児童扶養手当や生活保護の支給を受けていますが、定期運賃が割引になるのですか。」
JR以外の交通機関でも、割引制度が設けられている場合があります。
たとえば東京都では、児童扶養手当を受けているひとり親家庭は、世帯一人のみを対象に、「都営交通無料乗車券」が発行されます。
この乗車券があると、都営地下鉄全線や都バス、都電などの都営交通を無料で利用することが可能です。
発行手続きや利用方法などについては、東京都交通局のホームページをご覧ください。
(参考)東京都交通局:「都営交通無料乗車券」
7. 粗大ごみ処理手数料の減額または免除
児童扶養手当の支給を受けている世帯のひとり親家庭は、粗大ごみ処理手数料が減額または免除の対象となる場合があります。
自治体によって、実施の有無が異なります。まずは窓口やホームページなどで確認しましょう。
手続き内容も自治体によって異なりますが、多くの場合、粗大ごみ収集センターが窓口です。
受付時に減免の対象であることを伝えると、必要書類が送られてきます。必要なものを用意して申請すれば、減免制度を受けることができます。
粗大ごみを出す場合は、お住いの自治体に減免制度があるかどうかを調べてみましょう。
収入が少ない方を対象とした支援制度
ひとり親家庭だけを対象とした制度ではありませんが、収入が少ない方を対象とした支援制度もあります。条件を満たす場合は、必要な手続きを行いましょう。

8. 国民健康保険料の軽減・減免
一定の条件を満たすと、国民健康保険料の軽減・減免の対象となります。軽減は国、減免は自治体が設けている制度です。それぞれについて解説します。
(1)国民健康保険料の軽減
国民健康保険料の軽減とは、所得が一定の基準以下の場合、7割、5割または2割減額される制度です。
たとえば世帯所得が33万円以下の場合、国民保健料が7割減額されます。
所得の申告をしていれば、特別な手続きは必要ありません。自動的に国民健康保険料が軽減されます。
(2)国民健康保険料の減免
国民健康保険料の減免とは、特別な理由で保険料の支払いができなくなった世帯に対し、保険料の一部を減額または免除する制度です。
国民健康保険料の減免を受けるには、自治体への申請が必要です。世帯主の申請により、自治体が生活状況を調査して決定します。
まずは、窓口やホームページなどで、条件や詳しい内容を確認してください。
9. 国民年金保険料の免除や猶予
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請することで免除や納付猶予などを受けることができます。
手続をせずに国民年金保険料を滞納すると、将来に影響を及ぼします。
たとえば、年金を受け取ることができなくなる場合があります。未払い保険料の一括納付が必要になる場合もあります。
保険料の支払いが困難な場合はそのままにせず、市区町村役場の窓口や年金事務所などで相談しましょう。必要に応じて、免除や納付猶予などの制度を利用することをおすすめします。
(1)保険料免除
前年所得が一定額以下の場合は、申請が承認されると保険料の納付が免除になります。
ただし申請が通っても、必ずしも全額免除されるわけではありません。免除される額は、次の4種類です。
- 全額
- 4分の3
- 半額
- 4分の1
また免除期間に関しては、将来年金を受け取る際に支給額が減ることも、頭に入れておきましょう。
(2)保険料納付猶予
50歳未満で前年所得が一定額以下の場合、申請が承認されると、保険料の納付が一定期間のみ猶予されます。
ただし猶予期間がある場合、その分納める保険料が少なくなります。そのため、将来受け取る支給額が減ることを頭に入れておきましょう。
(参考)日本年金機構:「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」
働くための支援制度
厚生労働省では、ひとり親家庭の経済的な自立を助けるため、自治体と協力して就業支援に取り組んでいます。主な支援制度を3つ見てみましょう。

10. 自立支援教育訓練給付金
自立支援教育訓練給付金とは、働く意欲を持つ、ひとり親家庭の母または父に対して支給されるものです。
就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了すると、受講にかかった費用の一部が支給されます。
たとえば対象となる講座は、医療事務やパソコン資格、簿記資格、ホームヘルパーなどです。
給付金を受けられる講座は、厚生労働省のホームページで公開されています。ご確認ください。
(参考)厚生労働省:「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座」
なお自立支援教育訓練給付金を受け取る場合は、事前相談が必要です。受講を申し込む前に、必ず自治体の窓口で相談しましょう。
11. 高等技能訓練促進費
高等技能訓練促進費は、所定の資格をとろうと考える、ひとり親家庭の母または父に対して支給されるものです。
対象となる資格には、看護師や介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士などがあります。
これらの資格取得のため、一年以上かけて養成機関に通う場合、給付金が支給されます。給付金は次の2種類です。
- 高等職業訓練促進給付金・・・毎月支給(ただし上限3年間)
- 高等職業訓練修了支援給付金・・・修了後に支給
高等技能訓練促進費を受け取る場合は、事前相談が必要です。受講を申し込む前に、必ず自治体の窓口で相談しましょう。
12. マザーズハローワーク
マザーズハローワークは、子育てと仕事の両立を目指す母親のための公共職業安定所です。
マザーズハローワークには、働く母親に理解のある企業からの採用情報が集まっています。たとえば育児支援制度がある企業や、残業が少ない企業などが探しやすいのが特徴です。
おもちゃなどが置かれたキッズスペースや授乳室などもあり、子ども連れでも訪れやすい環境が整っています。
マザーズハローワークの所在地については、厚生労働省のホームページで公開されています。ぜひご確認ください。
(参考)厚生労働省:「マザーズハローワーク・マザーズコーナー」