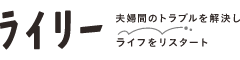離婚問題に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-037-079
- 慰謝料や養育費の適正額をアドバイスできる
- 早期解決が期待できる
- 書類作成や相手との交渉を代行できる
目次
養育費の支払い義務とは?
子どもを育てるには、食事や衣服だけでなく学費など、さまざまな費用が必要です。
こうした費用は、親権のない親も負担しなければなりません。「親権がないから」といって養育費を支払う義務が免除されるわけではありません。
これはきちんと法律でも決められています。
- <民法887条1項>
- 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
そもそも養育費は親権者と支払う側で内容を決めていきますが、親権者に対して支払うものではなく、あくまでも子どもへ支払われるべきものです。
したがって養育費は、親権者ではなく子どもが請求することも可能です。
また養育費は借金などではないため、自己破産をしたとしてもその義務を免れることはできません。
養育費は「どれくらい」支払う義務がある?
実は養育費の金額については「最低でも毎月●万円」というような法律上の決まりはありません。基本的には父母間の話し合いで合意した金額となります。
ただし、親は子どもに対して「生活保持義務」があるため、同等の生活水準で暮らせるような環境を与える必要があります。
たとえば養育費を受け取る側の親も働いていて、一定の収入があったとしても、養育費を払わなくていいというわけではありません。
親権者の生活水準のレベルが低ければ、自分の生活水準のレベルを落としてでも、養育費は支払う義務があります。
とはいえ、親と同等の生活水準がいくらかなんて簡単には決められませんよね。
そこで東京・大阪の裁判所は養育費の金額を決める基準として「養育費算定表」を公表しています。万が一、離婚裁判になったとしても、この算定表が参考になります。
ただし、「養育費算定表」はあくまでも目安です。どの家庭も事情はさまざまですので、養育費算定表だけですべてを決めるのではなく、あくまで父母間の話し合いの参考資料として用いるべきでしょう。
養育費は「いつまで」支払う義務がある?
親の扶養が必要な子どもを法律用語で「未成熟子(みせいじゅくし)」といい、未成熟子の間は親は養育費を支払わなければなりません。
問題はいつまでが未成熟子なのかということです。
未成熟子は一律に何歳までと定められてはいませんが、一般的には「子どもが経済的な自立を果たすまで」とされています。そのため成人(20歳)とは異なります。
たとえば、子どもが高校卒業して就職すると、経済的に自立していると見なされ、養育費の支払い義務は果たしたといえます。
一方で、障害を抱える子どもであれば、20歳を超えても経済的に自立して生活できない、つまり未成熟子になります。また大学生については、家庭裁判所では、ケースに応じて養育費の支払い義務は継続されると判断されています。
このように養育費の支払い期間は、親の収入や家庭環境、子どもの健康状態、就学状況など総合的に判断されます。
養育費は一括で支払うことも可能ですが、基本的には長期間支払い続けるものです。離婚協議では「20歳まで」と決めていても、子どもが大学への進学を希望する可能性もあります。
このような変化があった場合に対応できるよう、養育費は後から変更も可能になっています。
養育費の支払義務を放棄すると?
もしも養育費を支払わなかった場合、どのようなことが起きるのでしょうか?
親権がなくても養育費を支払うことは親の義務です。
したがって、もしも支払わなかった場合、親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。
差し押さえの対象となるのは、土地・家などの不動産や、家具・家電などの資産、現金などが挙げられます。
養育費の支払が原因による強制執行で最も多く見られるケースは、給料の差し押さえです。
給料が差し押さえられると、手取り額4分の1が勤務先から親権者に直接支払われます。勤務先から直接の支払なので、会社に養育費の支払を放置した事実が知られてしまうことにもつながります。
しかも差し押さえは強制的に行われるため、撤回できません。
養育費についての話し合いをしている時に公正証書を作成していた場合は、その公正証書自体に差し押さえできるほどの効力があります。
また、公正証書を作っていなかったとしても、受け取り側が申し立てを行った場合、調停・審判を通して養育費の支払いが命じられてしまうでしょう。
このように、養育費を支払わなかった場合には強制的に資産が差し押さえられてしまうなど、とても恐ろしいことが起きてしまうのです。
養育費の支払い義務を免れる方法はある?
真面目に毎月養育費の支払いをしていたとしても、予期せぬ事態が発生し、支払が滞る可能性もあります。
たとえば、養育費を支払う親が病気になったり、会社の業績不良による給料の減額などの事態に陥った場合はどのように対処すればいいのでしょうか?
また親権者が再婚しても、養育費を支払う義務は免除にならないのでしょうか?
養育費は子どもに対して親と同水準の生活を提供するのが義務ですから、以下のようなケースでは、免除が可能です。
- 相手が養育費を請求しないことに同意した
- 支払い能力がない場合
- 親権者が再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組した場合
それぞれ3つの方法を詳しくご紹介していきましょう。
1.相手が養育費を請求しないことに同意した
養育費に限らず、離婚協議は当事者間での合意が優先されます。
そのため、親権者が養育費を請求しないことに同意した場合は、支払い義務が免除されます。
もちろん親権者の合意が必要ですので、一方的に支払いの放棄はできません。
またもし相手が同意したとしても、話し合いだけでは水掛け論になりかねません。
その場合は合意時に公正証書という法的効力のある書面を作成しておいた方がよいでしょう。
また、養育費はあくまで子どもに支払われるものです。そのため父母間で養育費を請求しないと決めたとしても、子どもから請求があった場合は養育費の支払い義務が生じます。
2.支払い能力がない場合
養育費は「子どもに対して親と同水準の生活を提供するのが義務」という観点から、養育費を支払う人の収入がない場合も免除が可能です。
たとえば病気で働けなくなったなど、本人に支払い能力がないと認められた時点で義務を免れることができるのです。
ただし、現段階で働いていなかったとしても、働ける能力・潜在的稼働能力があると認められた場合には、養育費を支払う必要があるでしょう。
潜在的稼働能力の判断は、基本的に健康な成年であれば稼働能力があると認められます。そのため、自分の意思で会社を辞めて無職になったとしても養育費の支払い義務は発生するのです。
3.親権者が再婚し、再婚相手が子供と養子縁組した場合
親権者が再婚した場合も、養育費の支払い義務が免除される可能性があります。
なぜなら、再婚によって子どもの扶養義務が実親から再婚相手に移るからです。
ただし、扶養義務が再婚相手に移るのは、子どもと再婚相手が養子縁組を結んだ場合に限ります。
ただ親権者が再婚しただけでは、扶養義務が移るわけではありません。
また養子縁組を行ったとしても再婚相手に十分な資力がなかった場合、養育費の支払い義務が生じることもあります。
相手が再婚したからといって養育費の支払いに応じないとなると、強制執行で資産が差し押さえされてしまう可能性もあります。親権者が再婚したとしても、父母間で養育費の支払いについてしっかり話し合う必要があります。
養育費の義務を免除するのは難しいが減額は可能
ここまでお話ししたとおり、大きな理由がない限り、養育費の支払い義務が免除にするのは難しいといえるでしょう。
しかし、免除とまでは行かなくても正当な方法で減額の請求はできます。
養育費の減額請求ができるのは、以下のようなケースです。
1.支払い側の収入が減った
養育費の支払いを続ける中で会社が倒産してしまったり、大幅な減給に遭う可能性がないとはいい切れません。
上記でもご紹介したように、余程の理由がなければ支払い側の収入が減ったとしても養育費が免れるわけではありません。しかし収入が減った時に養育費の減額は可能です。
2.受け取り側の収入が増えた
先ほどお話しした養育費の算定表は、両親それぞれの収入を考慮して策定されています。
そのため、養育費の支払いを受ける親権者の収入が増えた場合も減額請求が行えます。 親権者が就職・転職したり、事業で成功して収入が大幅に増えた場合などは、まずは両者で話し合いする余地は十分にあります。
3.養育費を支払っている親が再婚し、扶養家族が増えた
養育費を受ける親権者が再婚した場合は、免除の可能性はありますが、支払っている側の親が再婚しても免除される可能性はないといっていいでしょう。
ただし養育費を支払っている側の親が再婚し、子どもを産んだ場合は減額の対象となります。
支払っている側が再婚した場合、配偶者が扶養家族となり、養っていく必要があります。
子供の養育費だけでも支払いが大変な場合は、扶養家族が1人増えたら養育費の支払いが困難になってしまう可能性もあるでしょう。 特に、自分と再婚相手に子供が生まれた場合、負担はより大きなものとなるので、原則養育費の減額請求が行えます。
【まとめ】養育費の話し合いがうまくいかないときは弁護士へ相談
たとえ離婚したとしても親である以上、子どもが自立するまでの間、養育費の支払いは義務です。
ただし、離婚してから子どもが自立するまでは、長い期間を要するケースもあります。
その間にどんな人生の転機が訪れるのかは誰にもわかりません。
もちろん親権者として子どもを育てるのは大変ですが、かといって別居している子どもに養育費を払い続ける苦労もなんら変わらないのです。
離婚時に決めた養育費の支払い義務が果たせない場合は、放置するのではなく、適切に対応する必要があります。
養育費の支払いは、法的に父母間での合意があればいつでも免除・減額は可能です。
とはいえ、お金の話となると話し合いだけで解決できない可能性はあります。離婚時にもめてしまい、疎遠になってしまったならなおさらでしょう。
免除や減額の正当な理由があっても、話し合いで解決できない場合は家庭裁判所による調停や審判で決めることになります。
しかし、書類作成から調停委員や裁判官とのやりとりなどは、法律の知識や経験がなければ困難を極めます。どんなに正当な理由であっても、現実には認められないケースもありえるのです。
もし話し合いで決着がつかないような場合は、法律の専門家である弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?