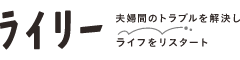浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

相手に面会交流権について理解してもらう
すでに面会交流を実施していた場合はこの限りではありませんが、相手が一方的に子どもとの面会交流を拒否する場合、面会交流権について正しい理解をしていない可能性があります。
子どもの親である以上、自身は子どもと面会交流する権利を持っており、また、子どもも自身と面会交流する権利を持っているのだということを、相手によく理解してもらいましょう。
子どもが健全な発育をしていくためには、父母両方の協力と努力が必要であることを伝えてみてください。
子どもが会いたくないと言っている場合
子どもが会いたくないと言っていると告げられてしまった場合、自身の行動の中に子どもの負担となってしまうようなことがなかったかよく考えてみましょう。
思い当たる節があるのであれば、反省していることを相手に伝え、もう一度、子どもに面会交流を呼びかけてもらいましょう。
しかし、現実には相手が面会交流を止めさせたいばかりに、子どもが会いたくないと嘘をついているといったことも考えられます。
また、子ども自身も、中学生くらいになってくれば共に暮らしている親に感情移入するようになり、離れて暮らす親との面会交流を避けたくなってしまった、なんてことも考えられます。
このように、子どもが会いたくないと言っている場合、非常に難しい問題を含んでいる可能性が考えられるため、可能であれば弁護士を通じて面会の交渉をしてもらうことをおすすめします。
理由がまったくわからない場合
相手がなぜ面会交流を拒否しているのか、その理由がまったくわからない場合、調停を申し立てて面会交流を求めるという方法が良いでしょう。
相手が理由を話してくれないとなれば、当事者のみで面会交流の話し合いをするのには限界があります。よって、家庭裁判所の調停手続きを利用し、調停の中で詳しい事情を探る、または、家庭裁判所の調査官に調査をしてもらいましょう。
もちろん、過去に面会交流の調停を経ていた場合であっても、再度、調停を利用することは可能となっています。
事情は常に変わっていくものなので、過去に調停を利用していたからといって、もう1度利用することができないなんてことはありませんのでご安心ください。