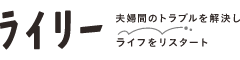浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

なぜ、もう一方の親が親権者になれないのか?
子どもがまだ成人していない場合、親権を行う者が必ずいなければなりません。
しかし、冒頭で説明したように、離婚をしていたような場合、親権者を持つ者が死亡したからといって、もう一方の親が必ずしも親権者になれるわけではありません。これはなぜでしょうか?
そもそも親権とは、子どもを監護し、教育する権利義務のことを言います。そして親権者は、住居や財産管理、契約行為の代理といった、子どもが日常生活をしていくうえで必要となる様々な行為に対して責任を負うことになっています。
親権は常に子どもの健全な成長のために行使されなければならず、離婚時に親権を取得していた者が亡くなったからといって、もう一方が上記の条件を満たしているとは限らないため、当たり前のように親権者になれるわけではないのです。
親権者として適格ではないと裁判所に判断された場合、「未成年後見」という制度により、もう一方の親の代わりに、裁判所に指定された人が子どもをみていくことになります。
未成年後見制度とは?
では、未成年後見とはどういった制度のことを言うのでしょうか?
未成年後見制度とは、親権を行う者がいなくなってしまった子どもに対して、親権と同様の権利義務を負った、「未成年後見人」を指定する制度です。親の代わりに、未成年後見人は子どもの監護教育、財産管理、契約行為の代理などをおこなっていきます。
未成年後見人が指定された後は、定期的(1年毎が多い)に裁判所に未成年後見人として行ってきた職務(財産の管理状況など)を報告し、この報告は子どもが成人に達するまで行われることになっています。
場合によっては、「未成年後見監督人」といって、初めて職務を行う未成年後見人をサポートするために、裁判所から弁護士といった専門家が選任されることもあります。いずれも子どものために作られた制度と言えるでしょう。
子どもに近しい親族が未成年後見人に
上記の例でいうと、もう一方の親が親権者として適格ではないと裁判所に判断されてしまった場合、子どもに近しい親族が家庭裁判所に未成年後見人選任の申立て(要求)を行い、そのまま未成年後見人として指定されることがほとんどとなっています。
なお、未成年後見人については申し立て時に候補者を立てることができるのですが、こちらも親権者と同様、適格でないと判断された場合、希望が通らないこともあります。
こういった場合は、申立てをした家庭裁判所の管轄内で活躍する、弁護士といった専門家が選任されることになっています。