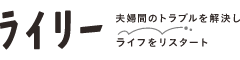浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

目次
そもそも親権とは?
単に親権といっても、きちんと意味を理解している方は少ないです。
というのも、親権というのは単に子どもの親であるという権利ではありません。
法律上は、子どもの身の回りの世話や教育への責任を負うという、「身上監護権」、子どもの財産を管理したり、法的な手続きを代理で行ったりする、「財産管理権」、という2つの権利から成り立っているのです。
しかし、親が離婚をするとなると、これらの権利を2人の親が共同で行使するわけにもいかないことから、夫婦のどちらかを親権者として指定する必要があるのです。
親権者と監護権者を別々に指定できる
なお、親が離婚をする際、親権者と監護権者を別々に指定することが可能となっています。
どういうことかというと、たとえば、親権者が父親となったが出張が多く、子どもと接する時間を多く作ることが出来ない場合、代わりに母親が監護権者となり、子どもに寄り添って生活をするといったことが可能になっているのです。
ただし、原則は、監護権は親権の一部となっていますので、通常は親権者が監護権者も兼ねるべきとされています。よって、親権者と監護権者を別々に指定ができるのは、特別な事情がある場合に限られています。
親権者はどのように決められる?
夫婦の話し合いによって親権者の指定ができなかった場合、親権者の指定は調停手続きへと持ち込まれることになります。
さらに、調停でも親権者が決まらなかった場合は、裁判官が強制的に判断をする審判へ、そして審判に対する反対意見(不服)が出た場合は、夫婦間の争いによる裁判へと移行していくことになっています。
もちろんこの間、夫婦は離婚をすることができません。
裁判所に親権者として認められるには
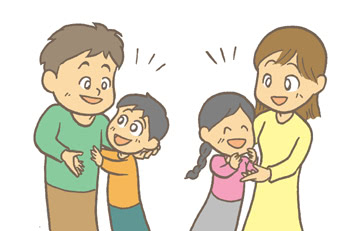
裁判所側に親権者として認めてもらうには、下記のように子どもへの利益が考慮されることになっています。
・子どもへの愛情
・子どもを育てていけるだけの経済力
・自身以外に子どもの面倒を見られる者の有無
・子どもの年齢と生活環境(学校など)
・子ども本人の意見(15歳以上の場合)
・兄弟姉妹の現在の状況など
上記事項をもとに総合的に判断されますが、実際は、子どもの年齢によって、
・8~9歳まで → 母親が親権者
・10~15歳まで → 基本的には母親が親権者だが、本人の意思も考慮
・15歳以上 → 本人の意思
となることが多く、母親が有利といえます。
とはいえ、子どもがすでに父の実家で暮らしており、祖父母が面倒をみてくれているといった状況であれば、環境を変えないように配慮され、父親が親権者として指定されることもあります。