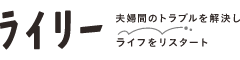浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

ただし、いきなりの審判は認められないことも・・・
調停が不成立となった場合、自動的に裁判官の判断による審判手続きへと移行されることになっていますが、冒頭のように、いきなり審判を申し立てることも可能となっています。
しかし、いきなり審判から申し立てをした場合、提出された申立書の内容や疎明資料によっては、審判ではなく、調停が優先されてしまうこともあるため注意しましょう。
つまり、子の引き渡し審判の申立は、事前の調停不成立が必須なわけではありませんが、話し合いが困難で調停を開くことに意味がないなど、先に審判を申し立てなければならないほどの理由がない限り、調停手続きへと回されてしまう可能性があるということです。
離婚の前後で若干の違いがある
次に、離婚の前後で子の引き渡しには若干の違いがあることも覚えておきましょう。
そもそも、子の引き渡しというのは、離婚の成立とは関係なく生じ得る問題です。
たとえば、離婚前であっても夫婦が別居状態であれば、どちらかから子の引き渡し請求があってもおかしくはありません。
また、離婚後であっても、子に対して健全な養育が行われていないとなれば、親権者でなかったとしても戸籍簿上の親である以上、子の引き渡し請求があってもおかしくはないのです。
少し話がそれましたが、離婚の前である場合、子の引き渡しを請求するのであれば、「監護者の指定」についても求めることになります。子の世話をするのが子の「監護者」になります。
よって、子の引き渡しと併せて監護者の指定についても求める必要があります。
すでに離婚後である場合は、監護者でない親は子の親権者として指定されていないことが多いと言えるため、子の引き渡し請求と共に、「親権者の変更申立て」(詳しくは「親権者や監護者は後からでも変更できる?」)も求める必要があることを覚えておきましょう。
子の引き渡しは弁護士に相談しよう
最後に、子の引き渡しというのは、最終的に人身保護請求という裁判手続きにまで発展してしまう可能性を含んでいます。
そして、この人身保護請求というのは、弁護士が代理人になっていなければならないという原則があります(詳しくは「人身保護請求の流れと判断基準とは?」)。
よって、より確実な子の引き渡し請求を検討しているのであれば、子の引き渡し調停(審判)を申し立てる前の段階から、弁護士に相談をしていたほうが良いことも覚えておくと良いでしょう。