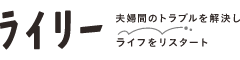浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

訴状が相手に送達されると
裁判所に訴状を提出すると、その訴状は相手にも必ず送付されなければなりません。
郵便局のオプションの1つである特別送達で送ります。
法律用語では、これを単に「送達」と言います。
送達で送られた書面を相手が受け取ると、相手は裁判所から指定された期間内に、訴状に対する回答である「答弁書」を提出しなければなりません。
裁判所は答弁書の内容を確認し、必要があれば離婚条件などの確認を双方にし、和解によって離婚ができないか?という協議離婚の可能性を模索します。
それができないと判断した時点で、実際に裁判手続きが進められていくことがほとんどとなっています。
裁判所での流れについて
裁判が開かれる日のことを「口頭弁論期日」と言います。
この口頭弁論期日に、双方の主張と証拠書類の提出、本人や証人による尋問(口頭で問いただすこと)といった証拠調べが行われ、裁判が進行していくことになっています。
双方の主張と証拠が出そろったところで、その内容を審理し、裁判官が最終的な判決を下すというのが裁判所での流れです。
なお、裁判というのは原則として公開されます。
しかし、裁判離婚の場合、夫婦間のプライバシーに考慮し、一部の事項については非公開で行われることも多くなっています。
判決後の流れについて
裁判離婚は、判決の確定によって離婚が効力を生じることになります。
確定までの期間は、判決書が当事者に送達された翌日から2週間となっています。
これを「控訴猶予期間」と言います。
ここで、夫婦双方から再度の審理を求める控訴(詳しくは「離婚の流れ」)がなければ、判決は確定し、法律上の離婚の効力が生じます。
しかし、この時点では戸籍上に離婚の事実が反映されておらず、判決の確定から10日以内に市区町村役場に「判決書の謄本(原本を複写したもの)」、「判決確定証明書」、「離婚届」を出すことによって、戸籍上も離婚が反映されることになっています。
なお、上記書類の取得方法については審判離婚時とほぼ同様となっているため、こちらの記事(「審判離婚の流れは?」)を参考にしてください。ただし、審判と裁判では管轄となる裁判所が異なっていることもあるため(詳しくは「裁判離婚はどこの裁判所に訴える?」)、裁判を行った裁判所で申請するようにしましょう。