過失割合9:1はどのような交通事故?10:0に変更できる可能性は
交通事故が発生すると、その責任は事故当事者の双方が負うケースが多くあります。
それぞれの責任の度合いを示す割合が「過失割合」で、9:1(9対1、90:10)、8:2(8対2、80対20)などと表記されます。
過失割合は最終的に受け取ることができる損害賠償額にも影響するため、相手側の保険会社の言い分に納得できないことも少なくありません。
この記事では、過失割合の事例や、納得できない場合の対処法などを解説します。
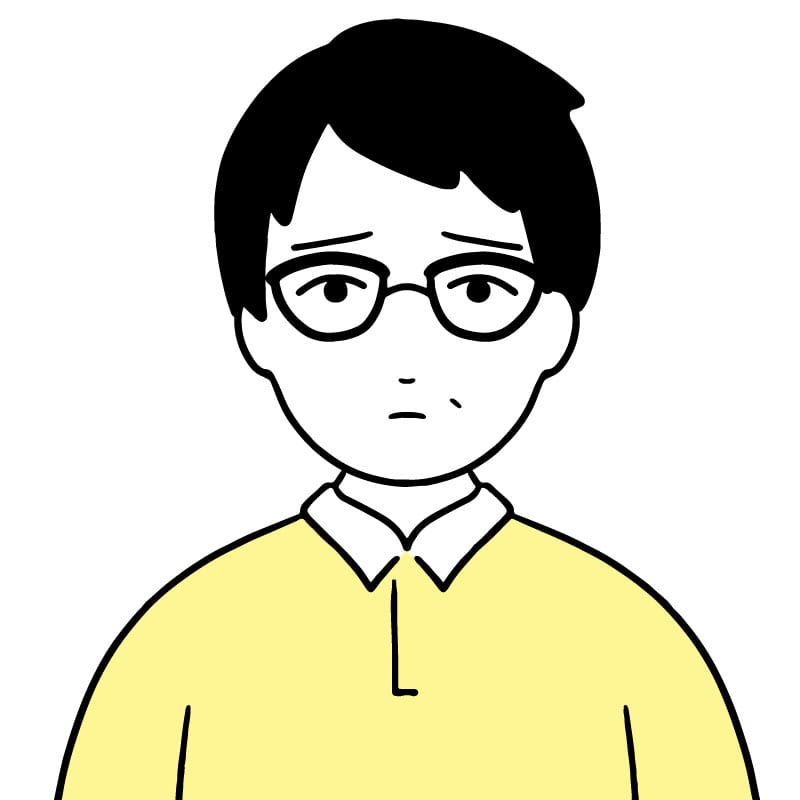

- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中
目次
過失割合9:1とはどのような交通事故?他の過失割合との比較
交通事故には、車対車の場合や車対歩行者の場合などさまざまなケースがあります。
それぞれの交通事故のケースにおいてどのような過失割合が認定される傾向にあるのかを理解しておくことが重要です。
交通事故のケースごとに、どのような過失割合が認定されたかについて、具体例を紹介します。
過失割合が9:1の事例
過失割合が9:1(相手:ご自身)となる交通事故の具体例として、以下のようなパターンが挙げられます。
【車対車】
信号機により交通整理の行われていない交差点における事故のうち、一方(ご自身)が優先道路のケース
【車対自転車】
交差点において、同一方向の左折した車(相手)と直進した自転車(ご自身)のケース
【車対歩行者】
駐車スペース内での車(相手)と歩行者(ご自身)のケース
交通事故は車対車、車対歩行者などさまざまなケースで発生しますが、各当事者の負う注意義務の内容と義務違反の態様・程度で過失割合が決まる部分があります。
車対自転車または車対歩行者の事故の場合は、大きな被害を受ける可能性があるのは、自転車や歩行者の側ですから、車の運転車側に相対的に重い注意義務が課されています。
車どうしの事故の場合は、どちらが優先道路を走っていたかなどが重視されます。
過失割合が8:2の事例
次に、過失割合が8:2(相手:ご自身)となる交通事故の具体例について見ていきましょう。
【車対車】
信号機による交通整理の行われている交差点における事故のうち、右折車(相手)・直進車(ご自身)がともに青信号で交差点に進入したケース
【車対自転車】
信号機により交通整理の行われている交差点における直進車同士の出会い頭事故のうち、自転車(相手)が赤信号、車(ご自身)が青信号のケース
【車対歩行者】
信号機の設置されている横断歩道上の事故のうち、車(相手)が赤信号で横断歩道に進入し、歩行者(ご自身)が赤信号で横断を始めたケース
車と自転車・歩行者の交通事故で過失割合が8:2となるケースは、自転車・歩行者側が赤信号で横断しようとしていた場合などが挙げられます。
車どうしの接触事故では直進車や左折車の走行が道路交通法では優先されるので、右折車の側に重い注意義務が課せられます。
他方で、直進車や左折車の側にも、対向車に注意して運転する義務が課せられている結果、過失割合は8:2となるのです。
過失割合が10:0の事例
過失割合が10:0(相手:ご自身)となるケースについても見ていきましょう。
【車対車】
信号機により交通整理の行われている交差点における直進車同士の出会い頭事故のうち、赤信号車(相手)と青信号車(ご自身)のケース、追突事故のケース
【車対自転車】
信号機による交通整理の行われている交差点における交差点における直進車同士の出会い頭事故のうち、交差点に赤信号で進入した車(相手)と、青信号で進入した自転車(ご自身)のケース
【車対歩行者】
信号機の設置されていない横断歩道上の事故のケース
車どうしの事故であれば、赤信号の車が進入してきて接触した場合や、追突事故(もらい事故)などが挙げられます。
車と自転車・歩行者との交通事故においても、車を運転する側が赤信号無視などを行った場合に、過失割合が10:0となるケースが多いといえるでしょう。

弁護士の〈ここがポイント〉
交通事故を巡る過失割合は、車対車や車対歩行者といった関係性や義務違反の態様などで大きく変わってきます。
典型的なパターンにぴったり合致する事故であれば過失割合の判断は行いやすいといえますが、個別の状況も絡んでくるのでていねいに判断をしていく必要があります。
過失割合の判断に迷ってしまうときは、交通事故案件に詳しい弁護士に相談をしてみましょう。
過失割合で損害賠償金が変わるの?計算例を紹介
過失割合を巡ってもめてしまう理由は、過失割合に応じて受け取ることのできる損害賠償金(示談金)の額が変わるからです。
損害額が大きいほど、過失割合のわずかな違いでも示談金額に差が生まれてしまいます。
そのため過失割合について納得しないまま示談をしてしまうと、後から悔やむことになりかねません。
納得がいくように話し合いを進めていくことが重要です。
過失割合の違いによって、具体的に示談金の額がどの程度変わってくるのかを見ていきましょう。
示談金の計算は、総損害額から過失相殺分を差し引くことで算出します。
総損害額をそのまま受け取れるというわけではなく、過失割合分を差し引いた金額を受け取れる仕組みです。
たとえば加害者の損害額を200万円、被害者の損害額を1,500万円、過失割合を9:1としたときに受け取れる示談金を計算してみましょう。
※加害者=過失割合が大きい当事者、被害者=過失割合が小さい当事者としています。
| 加害者 | 被害者 | |
|---|---|---|
| 過失割合 | 90% | 10% |
| 損害額 | 200万円 | 1,500万円 |
| 過失相殺後の金額 | 20万円 (200万円×0.1=20万円) |
1,350万円 (1,500万円×0.9=1,350万円) |
| 受け取れる金額 | 0万円 | 1,330万円 (1,350万円-20万円) |
次に、同じ条件で過失割合が8:2だった場合を計算してみましょう。
| 加害者 | 被害者 | |
|---|---|---|
| 過失割合 | 80% | 20% |
| 損害額 | 200万円 | 1,500万円 |
| 過失相殺後の金額 | 40万円 (200万円×0.2=40万円) |
1,200万円 (1,500万円×0.8=1,200万円) |
| 受け取れる金額 | 0万円 | 1,160万円 (1,200万円-40万円) |
上記の計算例の場合、過失割合が9:1と8:2では最終的に受け取れる示談金が170万円も違ってきます。
過失割合によって示談金の金額が異なる点をしっかりと押さえておきましょう。
過失割合はどうやって決める?
- 「過失割合」とは
- 交通事故が発生した原因について、当事者の責任の度合いを示した割合を指します。
では過失割合は、誰がどうやって決めるのでしょうか。
過失割合は当事者どうしで話し合うのが基本
過失割合は、交通事故の当事者どうしで話し合うのが基本です。
つまりご自身と相手方とで話し合う必要があるのです。
相手方の示談交渉を保険会社が代行する場合、一般の方はどう判断するべきかわからないことが多いため、相手の保険会社が一方的に過失割合を主張してくることがあります。
保険会社が提示してくる過失割合は、多くの場合は過去の事例(裁判例)を参考に判断していると考えられますが、被害者側の状況を的確に考慮していない場合もあります。
過失割合は被害者側が受け取ることのできる損害賠償金(示談金)の額に影響するため、保険会社は加害者側に有利な判断をする可能性があります。
過失割合は警察官が決めるのではない
交通事故現場に警察官が来るため、受け取ることのできる賠償金額を算定する際の過失割合は警察が決めるものという誤解もあるようですが、警察が決めるものではありません。
交通事故において警察官の役割は、実況見分調書の作成など、刑事事件としての交通事故事件の捜査活動であり、被害者が受け取ることのできる損害賠償金額を算定するための過失割合の認定については関与しません。
納得できないからといって警察官に相談しても、過失割合を変えることはできません。
過失割合に納得できない場合はどうする?
相手の保険会社が提示してくる過失割合に納得できないときは、安易に妥協してはいけません。
保険会社に対して粘り強く交渉することが大事ですが、うまく交渉を進められるのか不安に感じる場合もあるでしょう。
どのような対応策があるのかについて解説します。
相手側の保険会社と交渉する
過失割合は示談交渉によって決められるものなので、相手の保険会社と納得がいくまで話し合う必要があります。
しかし、やみくもに話をしても思うように主張が通らないことも多いといえます。
過失割合の見直しを提案するには、明確な根拠や修正要素などをもとに主張することが大切です。
それぞれのポイントについて解説します。
根拠を明確に示す
相手の保険会社と交渉を進める際に重要な点は、なぜ過失割合の変更が必要であるのかを明確な根拠をもって示すことです。
具体的な証拠としては、ドライブレコーダーの画像や目撃者の証言、実況見分調書などが挙げられます。
客観的な事実を示す証拠を提示することで、保険会社の担当者にも納得してもらう形で交渉を進めてみましょう。
気をつけておきたいのは事故発生から時間が経過すれば証拠集めが難しくなるため、できるだけ早めに行動を起こしたほうがよい点です。
思いがけないところから過失割合の変更につながる部分が出てくることもあるため、できるだけ多くの証拠を集めるようにしましょう。
修正要素を主張する
- 「修正要素」とは
- 基本となる過失割合を修正するための要素を指します。
プラスとなるもの(加算要素)だけでなく、マイナスとなるもの(減算要素)もあり個別の事情に合わせて見ていく必要があります。
〈修正要素の例〉
- わき見運転
- 酒気帯び運転
- スピード違反
- 直進車が交差点内に進入している状態で右折、右折車に加算
- 右折車が右折終了している状態で直進車が衝突。直進車に加算
-
(自動車対歩行者の事故)
- 夜間の走行
- 幹線道路
(自動車対自転車の事故)
- 二人乗りなど自転車側に大きな過失がある場合
などが挙げられます。
事故状況の結果から新たな事実が導き出せれば、相手の過失割合を加算する方向での修正を求めることができる可能性があります。
修正要素では状況に応じて、5~20%程度の過失割合に変動があるため、見逃せないポイントだといえます。
弁護士に相談する
過失割合の変更は、相手の保険会社との粘り強い交渉を進めていく必要があります。
しかし、一般の方が交渉に慣れた保険会社を相手に交渉を行っても、思うようにいかない場面もあるでしょう。
また高圧的な態度で示談成立を迫ってくる場合もあります。
どのように交渉を進めるべきかわからない場合は、交通事故案件に詳しい弁護士に相談をしてみるのも1つの方法です。
弁護士に相談をするメリットをさらに見ていきましょう。
裁判例等を確認して交渉してくれる
交通事故案件に詳しい弁護士に依頼すれば、示談交渉を任せられます。
過失割合についても、過去の裁判例などに照らしあわせて、的確に判断してくれるでしょう。
また必要に応じて、実際に事故現場に赴いて状況を確認したうえで保険会社と交渉してくれる場合もあります。
弁護士に依頼をすることで、保険会社との交渉を有利に進めることができる場合も少なくありません。
また保険会社との面倒なやりとりを弁護士に任せることで、精神的・時間的な部分で負担を軽減できるはずです。
【事例】弁護士に依頼して過失割合を変更できた例
弁護士に依頼することで、裁判例や現場の状況をもとに過失割合を変更できる場合もあります。
弁護士に依頼したことで、過失割合を8:2から9:1に変更できた事例を紹介します。
過失割合を変更できた事例
被害者:54歳(事故当時)女性・香川県
自転車走行中、脇道から出てきた脇見運転の車に接触して転倒。
病院では打撲、むちうちと診断され通院期間は約1年半に及びました。
当初相手の保険会社から提示された過失割合は8:2でしたが、自身は避けきれずに転倒したなどの状況から納得できず、弁護士に依頼。
相手側が脇見運転をしていたことなどを指摘して、過失割合を9:1に変更することができました。
弁護士費用特約を使えば弁護士費用がほぼ不要
弁護士に依頼をするメリットがわかっても、実際に依頼するには弁護士費用の負担が気になってしまうものです。
しかし自動車保険に付いている弁護士費用特約(弁護士特約)を利用すれば、弁護士費用の負担を気にすることなく依頼を行える可能性があります。

自動車保険にかぎらず、ご自身やご家族が加入する生命保険や火災保険、などの特約も利用できる場合があります。
弁護士費用特約では多くの場合で、一般的に上限300万円程度までの弁護士費用を保険会社が補償してくれます。
そのため、多くの場合に費用面の心配をせずに弁護士に依頼をすることができるのです。
弁護士法人・響でも、弁護士費用特約に対応しているのでお気軽にご相談ください。
早期解決のために片側賠償という方法もある
過失割合を決める際に、「片側賠償」といった方法を取ることもできる場合もあります。
- 「片側賠償」とは
- 過失割合を9:0とするなど、一方だけが過失割合に応じた賠償金を支払い、賠償金を支払った側は相手方に対する賠償請求を行わずに示談する方法です。
示談交渉をすみやかにまとめることができ、保険の等級にも影響を与えることがないのがメリットです。
一方で、本来受け取れたはずの金額に折り合いをつける必要があるため、状況に応じて判断する必要があるでしょう。
過失割合のよくあるQ&A
過失割合を巡っては、自分が被害者であるにもかかわらず、どうして責任が生じるのか納得いかない部分もあるでしょう。
しかし、過失割合は過去の判例や個別の事情に応じて決められるため、必ずしもすべての主張が認められるわけではありません。
過失割合について考えるうえでのポイントを解説します。
Q1 車どうしの事故では10:0にならない?
車どうしの交通事故では、追突事故(もらい事故)などのケースを除いては、過失割合が10:0となることは多くありません。
走行中の車が接触事故を起こしたときには、何らかの形で当事者の双方に責任が発生するものです。
そのため、示談交渉の場で過失割合が10:0になることを主張し過ぎてしまえば、なかなか話し合いがまとまらない原因になる恐れがあります。
話し合いをうまく進めるには、どのラインなら納得できるかをあらかじめ決めておくほうがよいでしょう。
Q2 停車中に追突されて過失割合9:1といわれたが合意すべき?
車を停車中に後ろから追突された場合は「もらい事故」となるので過失割合が10:0になる可能性があります。
しかし、もらい事故であればどのようなケースでも、過失割合が10:0になるわけではありません。
例えば、本来停車してはいけない場所で車を止めていた場合には、一定の責任を負う必要が出てくるでしょう。
合意すべきかどうかの判断は事故状況によるため、過失割合の変更には詳しい調査も必要になります。
どうしても納得できない場合は、交通事故案件に精通した弁護士に相談をしてみましょう。
Q3 すでに治療費などが払われている場合はどうなる?
示談交渉成立前でも、治療費などは相手の保険会社が病院に直接支払っている場合があります。
このようにすでに支払われた金額(既払金)がある場合は、過失相殺した後の損害賠償金額から差し引かれて支払われます。
治療中であっても、治療費の金額を的確に把握しておくとよいでしょう。
慰謝料の相場や事例について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。【関連記事はこちら】
『交通事故の慰謝料相場はいくら?入通院日数ごとの相場や事例を紹介』
【まとめ】交通事故の過失割合9:1のケースを理解して、納得いかない場合は弁護士に相談しよう
交通事故における過失割合は、示談金にも影響を与えるものなので慎重に判断する必要があります。
事故状況によっては過失割合がわずかに異なるだけでも、示談金の額に大きな違いが生まれる場合もあるからです。
相手側の保険会社から提示される過失割合をそのまま受け入れてしまうのではなく、納得がいくまで話し合いを進めることが大切です。
しかし交渉に慣れた保険会社を相手に交渉を進めるのは、一般の方には難しい部分があります。
思うように示談交渉を進められなければ、いつまでも補償が受けられずに不安な気持ちになってしまいがちです。
弁護士法人・響には、交通事故案件で豊富な実績を持った弁護士が在籍しています。
多くの事例を取り扱ってきたからこそ、さまざまなケースに対応可能です。
過失割合の判断は専門的な知識が必要な部分でもあるため、まずはお気軽にご相談ください。
※本メディアは弁護士法人・響が運営しています。
- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 保険会社との交渉を徹底サポート
- 24時間365日全国どこでも相談受付中


